「貿易業界唯一の国家資格」である通関士。その専門性に魅力を感じつつも、「2024年度の合格率が12.4%まで急落した」と聞いて、挑戦を躊躇していませんか?
あるいは、直近の2025年度試験の結果を見て、「自分にもチャンスがあるのか?」と情報を探しているかもしれません。
結論から申し上げます。2026年試験は、戦略的に学習を開始すれば、合格を勝ち取る「最大のチャンス」になります。
本記事では、2025年度の最新結果と、2025年6月から施行された歴史的な法改正(拘禁刑)、さらに最新の業界動向を踏まえ、2026年度試験に一発合格するための「真の難易度」を徹底解説します。
1. 【最新データ】通関士試験の合格率と「見かけの難易度」の正体
まず、直近4年間の試験結果を整理しましょう。ここには、多くの受験生が見落としがちな「カラクリ」が隠されています。
| 項目 | 2022年度(第56回) | 2023年度(第57回) | 2024年度(第58回) | 2025年度(第59回) |
|---|---|---|---|---|
| 総合合格率 | 19.1% | 23.6% | 12.4% | 15.1% |
| 全科目受験者 合格率 | 17.7% | 23.0% | 11.2% | 13.9% |
| 2科目免除者 合格率 | 63.8% | 72.4% | 61.3% | 67.2% |
「15.1%」という数字に騙されてはいけない
2025年度の合格率は15.1%まで回復しましたが、初学者が属する「全科目受験者」に限れば合格率は13.9%です。依然として、受験者の10人に1人強しか受からない難関であることに変わりはありません。
一方で、2科目免除者(実務経験15年以上のベテラン層)の合格率は約67%と非常に高く、彼らが全体の平均値を引き上げています。
2026年受験生への教訓:
「平均合格率」だけを見て安心せず、上位10〜15%に入るための「徹底した基礎固め」が必須です。
2. 他の国家資格との難易度比較(2024年度最新版)
通関士試験の立ち位置を客観的に把握するため、2024年度の他資格データと比較しました。
| 資格名称 | 合格率(2024年度) | 学習時間の目安 | 難易度の傾向 |
|---|---|---|---|
| 社会保険労務士 | 6.9% | 800〜1,000時間 | 膨大な暗記量と厳しい足切りがある最難関。 |
| 通関士 | 12.4% | 350〜500時間 | 法律知識に加え、実務の計算力が必須。 |
| 行政書士 | 12.9% | 600〜800時間 | 法律の登竜門。記述式問題の難易度が高い。 |
| 宅地建物取引士 | 18.6% | 200〜300時間 | 受験者層が広く、基礎知識の網羅が鍵。 |
通関士は合格率こそ行政書士に近いですが、学習時間はそれより短くて済む傾向にあります。これは、「通関実務」という特定の科目を攻略できるかどうかに合否が一点集中しているからです。
3. 【警告】2026年試験は「拘禁刑」への法改正対応が必須!
2026年試験を目指す方が、最も注意すべきなのが歴史的な法改正です。
2025年6月1日より、明治時代から続いてきた刑罰「懲役」と「禁錮」が廃止され、新たに「拘禁刑」へと統合されました。これにより、通関業法の「欠格事由(通関士になれない条件)」の文言も全て書き換わります。
- 旧法: 禁錮以上の刑に処せられた者
- 新法: 拘禁刑に処せられた者
注意!
2024年以前の古い問題集や、アップデートの遅い無料学習サイトで勉強していると、この用語の違いだけで失点するリスクがあります。2026年試験は、この「拘禁刑」が完全な試験範囲となります。必ず最新年度版の教材を使用してください。
4. 今、通関士を目指すべき「経済的メリット」
難易度の壁を越えてでも、今、通関士を取得する価値は急速に高まっています。
通関料25%値上げと待遇改善(2025年12月発表)
2025年12月、業界最大手のNX日本通運が、通関申告料金等を平均約25%値上げすることを発表しました(2026年1月より適用)。
これは、通関士の業務が「単なる書類作成」から、経済安全保障を守る「高度なコンプライアンス業務」へと再評価された結果です。
- 年収の向上: 業界全体での「賃上げ」の強力な根拠。30代で550万〜750万円を狙える求人が増加中。
- 売り手市場: 物流の「2024年問題」やEC貨物の爆発的増加に対し、有資格者が圧倒的に不足しています。
5. 結論:2026年合格への戦略的ロードマップ
通関士試験は、合格率の「揺り戻し」が顕著な試験です。2024年の歴史的な難化を経て、2025年、2026年は試験問題が平準化され、「正しく努力した人が確実に報われる年」になると予測されます。
合格を確実にするための3か条:
- 早期スタート: 学習時間350時間以上を確保するため、今すぐ(12月〜1月)開始する。
- 実務科目の克服: 独学で挫折しやすい「申告書作成」は、必要に応じて通信講座を活用する。
- 法改正の徹底: 「拘禁刑」などの最新情報に完全対応した教材・情報を入手する。
難易度に怯える必要はありません。今の「追い風」が吹いている時期に学習を開始し、一生モノの専門性を手に入れましょう。
次によく読まれている記事:
【2026年最新】通関士の通信講座おすすめ比較|失敗しない選び方
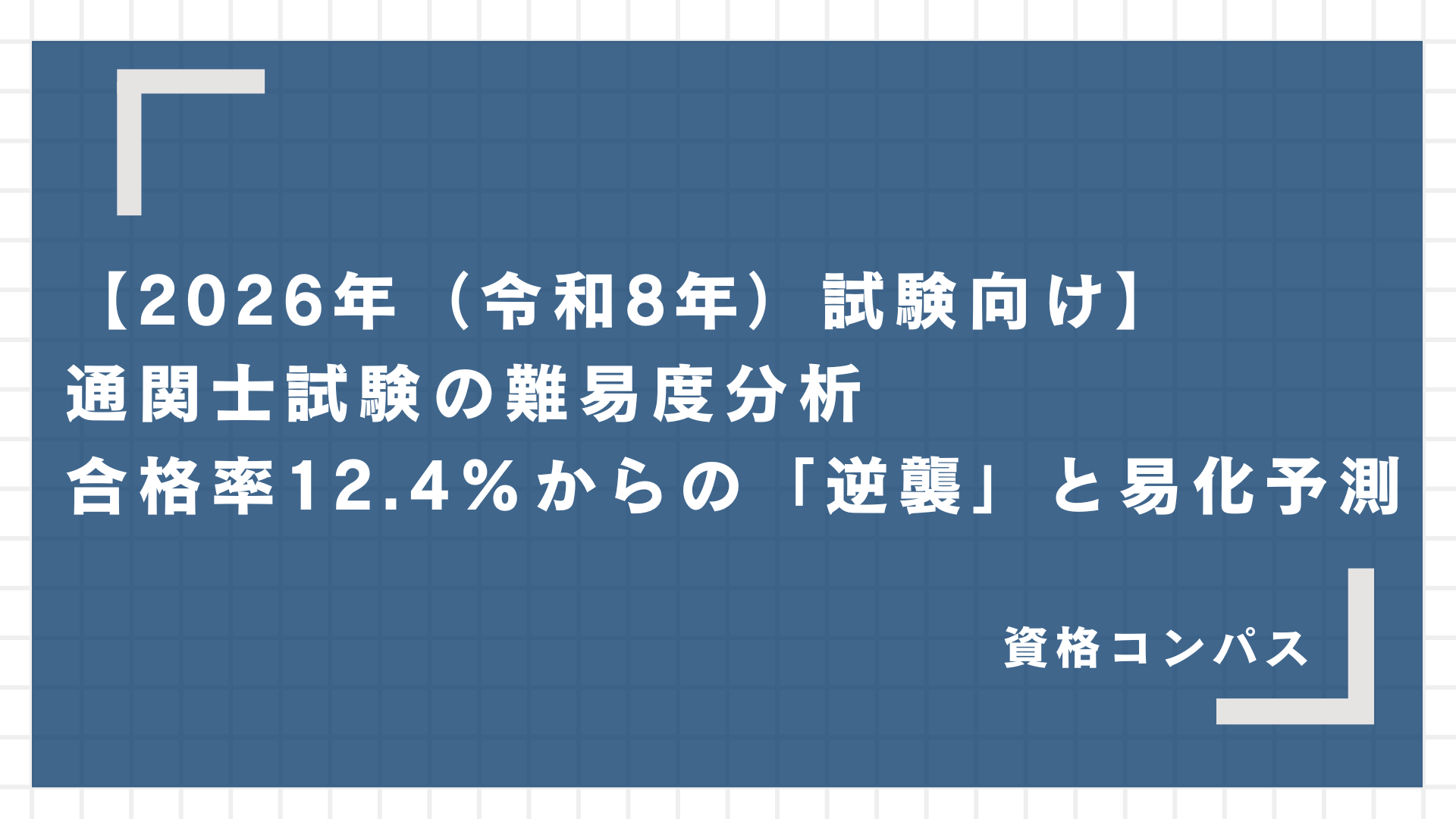


コメント