「FOB」「CIF」といったアルファベット3文字の記号を、貿易関連の書類で見かけたことはありませんか?
これはインコタームズと呼ばれる、世界共通の貿易取引ルールです。一見するとただの暗号に見えるかもしれませんが、国境を越えたスムーズな取引を実現するためには欠かせない、いわば貿易取引の「世界共通言語」なのです。
この記事を読めば、あなたもインコタームズの基本を完全に理解できます。
- なぜインコタームズが必要なのか
- 11種類ある規則の全体像
- 「危険負担」と「費用負担」という最重要ポイント
- 各規則の具体的な内容と実務上の注意点
通関士を目指す方はもちろん、貿易実務に関わるすべての方にとって必須の知識を、図を交えながらどこよりも分かりやすく解説します。
そもそも通関士とは?という点については、まずはこちらの記事で全体像を掴んでおくのがおすすめです。
インコタームズとは?なぜ貿易に不可欠なのか
インコタームズ(Incoterms)とは、国際商業会議所(ICC)が制定した、貿易取引における売主と買主の役割分担を定めた国際ルールです。
具体的には、貨物を輸出者(売主)から輸入者(買主)へ引き渡す過程で発生する、以下の2つの重要な範囲を明確にするために使われます。
- 費用負担:運賃や保険料、通関費用などをどちらがどこまで負担するのか。
- 危険負担:輸送中に貨物が壊れたり、なくなったりした場合、その損失をどちらが負担するのか(リスクの移転時点)。
もし、こうしたルールがないまま「日本の港で引き渡す」といった曖昧な契約を結んでしまうとどうなるでしょうか。船に積み込む前の費用は誰が払うのか、船に乗せた後に発生した事故の責任は誰にあるのか、といった解釈の違いから、国境を越えた大きなトラブルに発展しかねません。
インコタームズは、こうしたトラブルを未然に防ぎ、世界中の企業が安心して取引を行うための羅針盤の役割を果たしているのです。
【重要】インコタームズが「定めない」こと
インコタームズは非常に便利ですが、万能ではありません。物品の所有権がいつ移転するのか、代金をいつ・どのように支払うのか、契約違反があった場合にどうなるのか、といった点はインコタームズの範囲外です。これらは別途、売買契約書本体で明確に定める必要がありますので、ご注意ください。
【全体像】インコタームズ2020の11規則を2つのグループで理解する
現在使われている最新版は「インコタームズ2020」で、11の規則が定められています。これらは、利用できる輸送手段によって、大きく2つのグループに分けられます。
【図解】貿易の一般的な流れ
インコタームズ2020:11規則の2大グループ
🚚✈️🚢 あらゆる輸送手段用 (7規則)
- EXW (工場渡し)
- FCA (運送人渡し)
- CPT (輸送費込み)
- CIP (輸送費・保険料込み)
- DAP (仕向地持込渡し)
- DPU (荷卸込持込渡し)
- DDP (関税込持込渡し)
🚢 海上・内陸水路輸送限定 (4規則)
- FAS (船側渡し)
- FOB (本船渡し)
- CFR (運賃込み)
- CIF (運賃・保険料込み)
グループ①:あらゆる輸送手段に対応する7規則
船、飛行機、鉄道、トラックなど、単一または複数の輸送手段を問わずに利用できるグループです。近年のコンテナ輸送の多様化に対応しやすく、実務上、こちらのグループの規則が使われる機会が増えています。
- EXW (Ex Works) – 工場渡し
- FCA (Free Carrier) – 運送人渡し
- CPT (Carriage Paid To) – 輸送費込み
- CIP (Carriage and Insurance Paid To) – 輸送費・保険料込み
- DAP (Delivered at Place) – 仕向地持込渡し
- DPU (Delivered at Place Unloaded) – 荷卸込持込渡し
- DDP (Delivered Duty Paid) – 関税込持込渡し
グループ②:海上・内陸水路輸送に限定の4規則
在来船による輸送など、船での輸送に特化したグループです。貨物をコンテナに入れないばら積み貨物などで今も利用されていますが、現代のコンテナ輸送に適用するとリスクが生じる場合があるため注意が必要です。
- FAS (Free Alongside Ship) – 船側渡し
- FOB (Free On Board) – 本船渡し
- CFR (Cost and Freight) – 運賃込み
- CIF (Cost, Insurance and Freight) – 運賃・保険料込み
最重要ポイント!「危険負担」と「費用負担」の分岐点を理解する
インコタームズを理解する上で最も重要なのが、「危険負担」と「費用負担」の分岐点です。
- 危険負担(リスク)の分岐点
輸送中の事故などで貨物に損害が出た場合、どこから買主の責任になるかという境界線です。このポイントを過ぎてから発生した事故の損害は、買主が負担することになります。 - 費用負担(コスト)の分岐点
運賃や保険料といった輸送コストを、どこまで売主が支払い、どこから買主の支払いになるかという境界線です。
ほとんどの規則では、この2つの分岐点は同じ場所です。しかし、後述する「C」で始まる4つの規則(CFR, CIF, CPT, CIP)だけは、この分岐点が異なるため、特に注意が必要です。
【図解】インコタームズ「Cグループ」の重要ポイント
危険の移転は「輸出国側」で起こるのに対し、費用の負担は「輸入国側」まで続くのが最大の特徴です。
(輸出国)
(輸出港)
(輸入港)
(輸入国)
■ 危険(リスク)負担の範囲
■ 費用(コスト)負担の範囲
11規則を4つのグループ(E, F, C, D)でさらに深掘り
11の規則は、取引の性質によってさらに4つのグループ(E, F, C, D)に分類できます。アルファベットが進むにつれて、売主の負担が大きくなっていくイメージで捉えると理解しやすくなります。
Eグループ(出発地・引渡し)- 売主の負担が最小
このグループに属するのはEXWのみです。
| 規則 | 名称 | 危険と費用の移転場所 | ポイント |
|---|---|---|---|
| EXW | 工場渡し | 売主の工場や倉庫 | 売主の負担が最も軽い条件。売主は自身の施設で貨物を準備するだけでよく、積込み作業や輸出通関すら買主の責任となる。 |
Fグループ(主要輸送費・買主負担)- 輸出地の港やコンテナヤードで引渡し
主要な国際輸送(船や飛行機)の運賃は、買主が負担するグループです。
| 規則 | 名称 | 危険と費用の移転場所 | ポイント |
|---|---|---|---|
| FCA | 運送人渡し | 買主が指定した運送人(業者)に引き渡した時点 | コンテナ輸送で広く使われる、現在の実務で最も重要な規則の一つ。輸出通関は売主が行う。引渡し場所が売主の施設内の場合は売主が積込み義務を負いますが、それ以外の場所(港のターミナル等)では積込み義務を負いません。 |
| FAS | 船側渡し | 輸出港で、貨物を本船の横に付けた時点(海上輸送限定) | 在来船などで使われる。船に積み込む直前までが売主の責任。 |
| FOB | 本船渡し | 輸出港で、貨物を本船の甲板上に置いた時点(海上輸送限定) | 日本で古くから使われている最も有名な条件の一つ。ただし、現代のコンテナ輸送には不向きとされます。コンテナは船積みより前に港のターミナルで運送人に引き渡されるため、その時点から船に乗るまでの間にリスクの空白期間が生まれる可能性があります。コンテナ輸送の場合は、代わりにFCAの使用が強く推奨されます。 |
Cグループ(主要輸送費・売主負担)- 危険負担と費用負担の分岐点が異なる
主要な国際輸送の運賃を売主が負担するグループです。最大の特徴は、危険負担の移転場所(輸出地側)と、費用負担の移転場所(輸入地側)が異なることです。
| 規則 | 名称 | 危険の移転場所 | 費用の移転場所 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| CFR | 運賃込み | 輸出港で本船に積んだ時点 | 輸入地の指定港まで | 売主は輸入港までの運賃を負担するが、船に乗せた後の事故の責任は負わない。(海上輸送限定) |
| CIF | 運賃・保険料込み | 輸出港で本船に積んだ時点 | 輸入地の指定港まで | CFRの条件に加え、売主が輸入港までの貨物保険を手配・負担する。(海上輸送限定)ただし、売主が手配する保険は最低レベルの補償が原則です。コンテナ輸送の場合は、より手厚い保険が義務付けられているCIPの使用が推奨されます。 |
| CPT | 輸送費込み | 輸出地の運送人に引き渡した時点 | 輸入地の指定場所まで | 売主は輸入国の指定地までの運賃を負担するが、最初の運送人に渡した後の事故責任は負わない。 |
| CIP | 輸送費・保険料込み | 輸出地の運送人に引き渡した時点 | 輸入地の指定場所まで | CPTの条件に加え、売主が輸入国指定地までの貨物保険を手配・負担する。インコタームズ2020では、売主が手配する保険は最高レベルの補償(協会貨物約款A号条件など)が義務付けられ、買主保護が強化されました。 |
Dグループ(到着地・引渡し)- 売主の負担が最大
貨物を輸入国側まで運び、そこで引き渡すグループです。売主の負担が最も大きくなります。
| 規則 | 名称 | 危険と費用の移転場所 | ポイント |
|---|---|---|---|
| DAP | 仕向地持込渡し | 輸入国の指定場所(荷卸しの準備ができた時点) | 輸入通関と関税の支払いは買主が行う。 |
| DPU | 荷卸込持込渡し | 輸入国の指定場所(荷卸しが完了した時点) | インコタームズ2010のDAT(ターミナル持込渡し)から名称変更され、より柔軟な場所を指定できるようになった規則。荷卸し作業まで売主の責任で行う唯一の条件。 |
| DDP | 関税込持込渡し | 輸入国の指定場所(荷卸しの準備ができた時点) | 売主の負担が最大の条件。輸入通関と関税の支払いも売主が行う。 |
まとめ:インコタームズは円滑な貿易の羅針盤
最後に、この記事の要点をまとめます。
- インコタームズは、貿易取引における「費用」と「危険」の負担範囲を定めた世界共通のルール。
- 11の規則は、「あらゆる輸送手段用(7規則)」と「海上輸送限定(4規則)」に大別される。
- コンテナ輸送では、海上輸送限定の規則(FOB, CIF等)ではなく、あらゆる輸送手段用の規則(FCA, CIP等)を使うことがトラブル回避の鍵。
- 最重要ポイントは「危険負担」と「費用負担」の分岐点で、「C」グループの規則ではこの2つが異なる。
- E→F→C→Dの順に、売主の負担が大きくなっていく。
インコタームズは、通関士として働く上で必須の知識ですが、実際の現場では他にも様々なスキルが求められます。実務で求められるスキルについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
インコタームズを正しく理解し、輸送の実態に合わせて使い分けることは、不要なトラブルを避け、円滑な国際取引を行う上で不可欠なスキルです。通関士試験ではもちろん、実務においても極めて重要な知識ですので、ぜひこの機会に全体像を掴んでおきましょう。
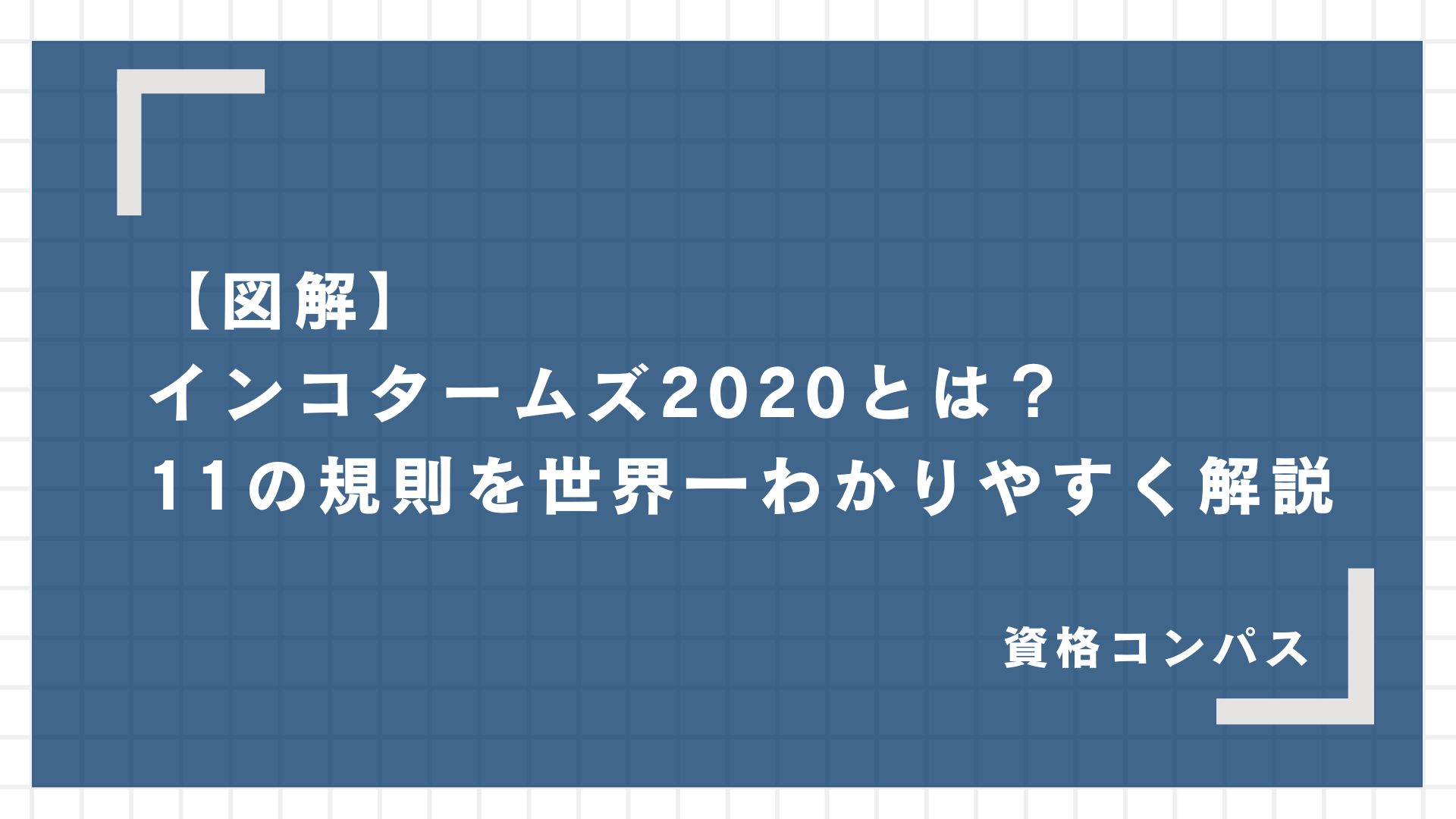

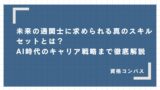


コメント