「自分の持っているテキスト、もしかして情報が古い…?」
「最近ニュースで話題の法改正って、今年の試験に出るんだろうか…?」
試験日が近づくにつれて、多くの受験生がこうした「法改正」に関する不安に直面します。どれだけ知識を積み上げても、その前提となる法令の情報が間違っていれば、元も子もありません。
しかし、安心してください。通関士試験の法改正には、追いかけるべき明確な範囲とルールが存在します。
この記事を最後まで読めば、あなたは以下の3つを手に入れることができます。
- 追うべき法改正の範囲が明確になり、余計な情報に惑わされなくなる
- 絶対に信頼できる公式情報源だけにアクセスする方法がわかる
- 法改正への不安から解放され、本来やるべき学習に100%集中できる
もう一人で悩むのはやめましょう。情報の荒波を乗りこなすための「羅針盤」を、ここでお渡しします。
通関士試験で問われる「法改正」の基本ルール
闇雲に情報を探す前に、まずは通関士試験における法改正の「絶対的なルール」を押さえましょう。これを知るだけで、あなたの不安の9割は解消されるはずです。
試験基準日(試験年の7月1日)を絶対に押さえる
最も重要なルール、それは試験で問われる法令は「その年の7月1日現在で施行されているもの」が原則である、という点です。
これは税関が毎年発表する「通関士試験公告」にも明記されている公式ルールです。
通関士試験の出題に係る法令等は、当該試験が行われる年の7月1日現在において施行されているものとします。
(出典:税関 Japan Customs | 通関士試験のお知らせ)
つまり、たとえ7月2日以降にどんなに大きな法改正が施行されたとしても、それは今年の試験範囲には含まれません。来年以降の試験で問われる可能性はありますが、少なくとも今は気にする必要は一切ないのです。
この「7月1日」という基準日を心に刻むだけで、「あのニュースの改正は範囲だろうか?」といった日々の雑音から解放されます。
なぜ法改正が重要なのか?過去の出題実績
では、なぜ法改正点が試験で狙われやすいのでしょうか。それは、法改正が国の通商政策や、より効率的な通関行政への変化をダイレクトに反映しているからです。
作問者側には、「新しいルールを正しく理解しているか」「社会の変化に関心を持っているか」という、実務家としての素養を測る意図があります。
過去には、以下のような法改正点が実際に出題されています。
- AEO(認定事業者)制度の対象者拡大
- 電子帳簿保存法の改正に伴う、帳簿類の電磁的記録による保存要件の変更
- 個人情報保護法の改正に伴う、通関業者の欠格事由の変更
このように、法改正点は「時事問題」としての側面も持ち合わせており、学習しておけばライバルに差をつけられる重要な得点源となりうるのです。
信頼度100%!法改正情報を確認する3つの一次情報源
「じゃあ、具体的にどこで情報を確認すればいいの?」という疑問に、完璧な答えを用意しました。以下の3つは、国が発表している「一次情報源」です。ネット上の不確かな情報に惑わされず、必ずこれらの公式サイトを確認するようにしてください。
① 税関 Japan Customs ホームページ
信頼度・重要度ともにNo.1の情報源です。通関士試験の実施機関である税関が直接発信する情報なので、ここに書かれていることがすべてと言っても過言ではありません。
特に以下のページは、定期的にチェックする価値があります。
- 通関士試験のお知らせ: 試験の基本情報に加え、大きな法改正があった年度には、特記事項が掲載されることがあります。
- 関税・外国為替等審議会: 関税法改正の「背景」や「理由」が分かる資料が公開されています。ただし、内容は非常に専門的で難解な場合が多いため、上級者向けの情報源と言えます。なぜこの法律が変わったのかを深く知りたい場合や、予備校の解説でも理解が難しい場合に参照するといった、補足的な使い方が良いでしょう。
② 税関ホームページ(実行関税率表・輸出統計品目表)
通関実務科目、特に輸出入申告書問題で満点を狙うなら、税関ウェブサイトで公開されているこれらの情報のチェックは必須です。関税率の変更や統計品目の改正情報などが掲載されます。
- 実行関税率表: 試験で使われる関税率表そのものです。大きな改正があった場合は、新旧対照表などが公開されます。
- 輸出統計品目表: 輸出申告で使う品目表です。こちらも改正情報を確認できます。
③ e-Gov法令検索
法律の条文そのものを、施行日ベースで正確に確認したい場合に使う、いわば「最終兵器」です。
- e-Gov法令検索: 例えば、「関税法」と検索し、強力な「時点指定」機能で「7月1日」時点の法令を表示させることができます。これにより、試験範囲の基準日における最新の改正が反映された条文を正確に読むことが可能です。
ただし、e-Govはあくまで法律の原文が掲載されているだけなので、どこがどう変わったのかを自力で探す必要があります。基本的には、次に紹介する予備校や教材の情報を活用し、その裏付けを取るためにe-Govを使う、というスタンスが良いでしょう。
予備校・市販教材の法改正対応をどう活用するか
一次情報源の重要性は理解しつつも、「正直、公式サイトを自分で調べるのは大変…」と感じるのが本音だと思います。そこで、受験指導のプロたちがまとめた情報を活用するのが最も賢い選択です。
通信講座・予校の「法改正情報」は最強の時短ツール
大手予備校や通信講座では、その年の試験に影響する法改正点を専門家が分析し、「ここだけは押さえるべき」という要点をまとめたレジュメや補足講義を提供してくれます。
これは、膨大な情報の中から重要なポイントだけを抽出してくれる、まさに「最強の時短ツール」です。独学で何時間もかけて調べる作業を、プロに任せることで、あなたは本来の学習に集中できます。どの講座を選ぶかによって、こうしたサポートの質も変わってきますので、慎重に検討することをおすすめします。
市販テキスト・問題集の「追補情報」を見逃さない
独学で市販の教材を使って学習している方も、諦める必要はありません。多くの出版社では、法改正に対応するための「追補情報」や「正誤表」を、自社のウェブサイト上でPDF形式で無料提供しています。
一度、ご自身が使っているテキストや問題集の出版社名で検索し、公式サイトにそうした情報が掲載されていないか確認してみてください。最新版を買い直さなくても、重要な法改正点をカバーできる可能性があります。
まとめ
法改正への漠然とした不安は、今日で終わりにしましょう。
- 追いかけるべきは「試験年の7月1日」までに施行された法律だけ。
- 情報源は「税関HP」を基本とし、申告書対策で同サイト内の「実行関税率表」などを確認。
- 最も効率的で確実なのは、予備校や教材が提供する「法改正まとめ情報」を活用すること。
法改正に過度に怯える必要はありません。正しい情報源とルールを知っておくことは、試験本番で迷わずに解答するための強力な「お守り」になります。
残された時間、あなたは法改正の調査に費やすべきではありません。これまで積み上げてきた知識の定着に、全力を注いでください。
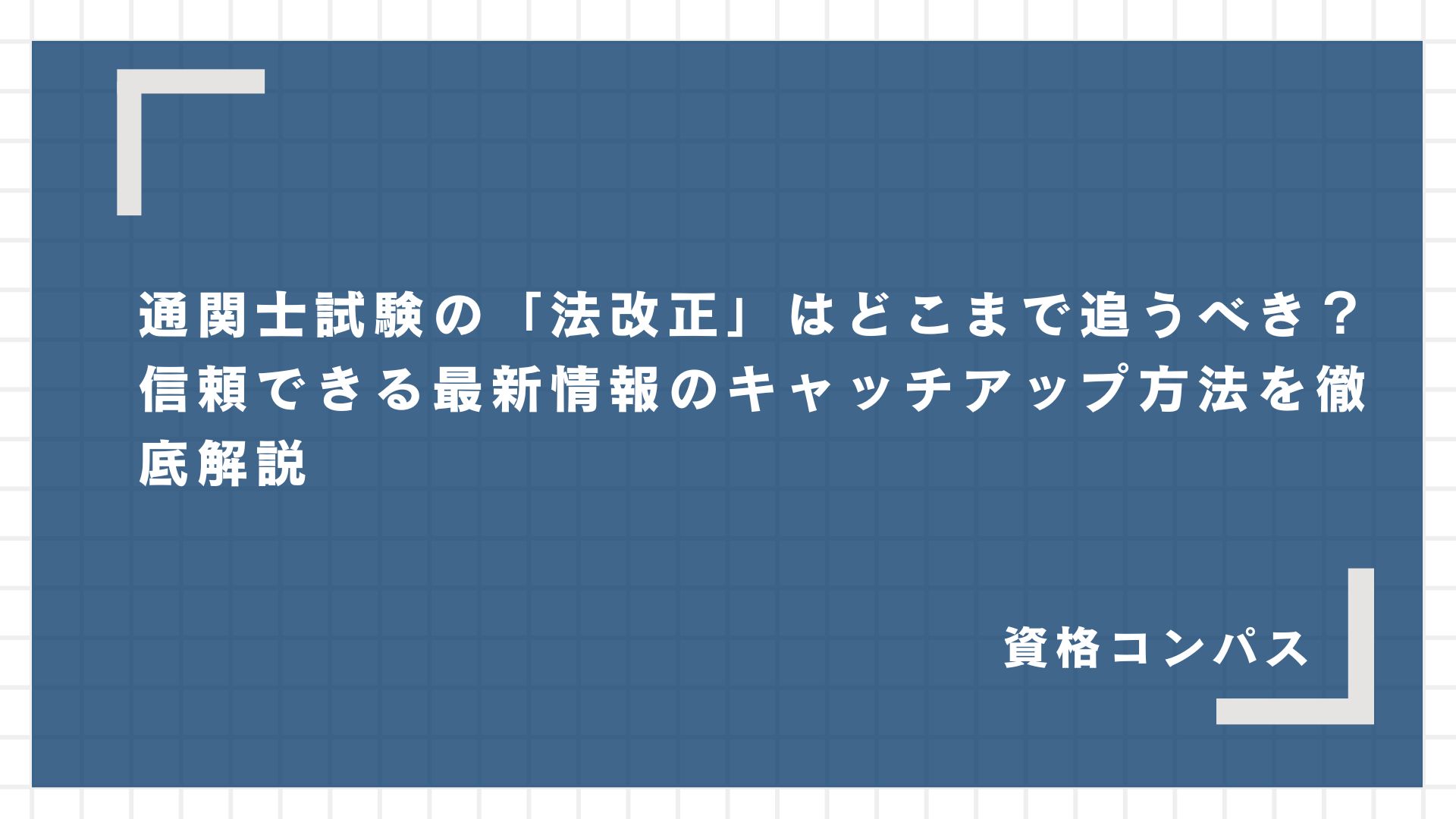


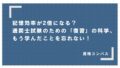
コメント