第59回通関士試験を受験された皆様、本当にお疲れ様でした。長い受験勉強を終え、今は解放感と同時に、結果に対する不安が入り混じった複雑な心境かもしれません。
この記事では、そんな皆様が今一番知りたい情報を網羅的にお届けします。
- 主要予備校の解答速報・分析会はいつ?
- 今年の試験の難易度は?(科目別レビュー)
- 合格基準点はどうなる?(ボーダーライン予測)
- 自己採点の結果、次に何をすべきか?
試験直後のこの時期を乗り越え、次の一歩を踏み出すための明確なガイドとして、ぜひ最後までお読みください。
試験終了直後、まずやるべき3つのこと
試験の出来栄えはどうでしたか?手応えがあった方も、そうでなかった方も、まずは落ち着いて情報を集め、客観的に自分の立ち位置を把握することが大切です。
① 各予備校の「解答速報」で自己採点
合格発表を待つ約1ヶ月間、自分の結果を予測するために最も重要なのが自己採点です。各資格予備校が試験当日の夜から翌日にかけて、ウェブサイト上で解答速報を公開します。
複数の予備校の解答速報を比較し、ご自身の解答と照らし合わせてみましょう。ユーキャンなどが提供する「自動採点サービス」を利用するのも便利です。
② 自己採点の重要性と注意点
自己採点は、あくまで予備校の見解に基づく「非公式」なものです。過去には、予備校間で解答が割れる(解答が異なる)問題も存在しました。
そのため、自己採点の結果に一喜一憂しすぎる必要はありません。特に、合格基準点をわずかに下回っている場合でも、後述する「合格基準点の調整(救済措置)」によって合格する可能性は十分にあります。
思うような手応えが得られず自己採点をためらう気持ちも分かりますが、まずは暫定的な結果を把握し、冷静に公式発表を待つ姿勢が大切です。
③ 主要予備校の解答速報・分析会スケジュールまとめ
主要な資格予備校が発表する解答速報や試験分析会のスケジュールを一覧にまとめました。専門家による詳細な解説は、今年の試験の全体像を把握する上で非常に役立ちます。
| 予備校 | イベント内容 | 日程 |
|---|---|---|
| TAC | 本試験講評会(YouTube Live) | 10月5日(日)19:00~ |
| フォーサイト | 解答速報・試験講評・自動採点 | 10月7日(火)15:00頃 |
| LEC | 解答速報 | 10月8日(水) |
| TAC | 解答速報 | 10月8日(水) |
| TAC | 解答・解説 | 10月13日(月・祝) |
| LEC | 試験分析会 | 10月18日(土) |
| TAC | 総評と科目別分析 | 11月10日(月) |
※最新の情報は必ず各予備校の公式サイトをご確認ください。
【速報】第59回通関士試験の難易度を科目別に徹底分析
今年の試験は全体として難しかったのでしょうか、それとも易しかったのでしょうか。近年の傾向を踏まえ、科目別に難易度を分析します。
全体的な難易度評価|今年は難化?易化?
通関士試験の難易度は、年によって大きく変動します。特に、合格率が24.2%と高かった第57回(令和5年)から、12.4%へ急落した第58回(令和6年)への変化は記憶に新しいところです。
この「揺り戻し」の傾向を踏まえ、第59回試験がどの程度の難易度に着地するのかが最大の焦点です。各予備校の講評会やSNS上の受験者の声から、全体的な難易度を推し量ることができます。
科目別分析①:通関業法
伝統的に3科目の中では比較的得点しやすいとされ、多くの受験者がここで高得点を目指す戦略的な科目です。択一式・語群選択式・複数選択式で構成され、基本的な条文理解が問われます。
今年の試験が例年通りの難易度であったか、それとも意表を突く難問が含まれていたかによって、受験者全体の平均点も変わってくるでしょう。
科目別分析②:関税法等
配点が最も大きく、例年、多くの受験者を悩ませる最重要科目です。難易度が高かった昨年の第58回試験では、この科目の合格基準点が60%→55%に引き下げられる「救済措置」が取られました。
この科目を終えた時点で「終わった…」と感じるほどの精神的ダメージを受ける受験生も少なくありません。今年の「関税法等」の難易度がどうだったかは、全体の合格ラインを予測する上で最大の注目ポイントとなります。
科目別分析③:通関実務
計算問題や申告書作成問題など、多様な形式で実践的な知識が問われる科目です。特に配点の大きい申告書問題で、見慣れない品目が出題されたか、特殊な評価ルールを適用する必要があったかによって、得点差が大きく開きます。
計算問題をいかに早く正確に処理できたか、そして申告書問題に冷静に対処できたかが合否を分ける鍵となります。
合格ラインの変動要因|合格率と合格基準点のカラクリ
自己採点の結果を見て最も気になるのが「結局、何点取れていれば合格なのか?」という点でしょう。ここでは、通関士試験の合格基準点がどのように決まるのかを解説します。
データで見る|通関士試験の合格率はなぜ毎年変動するのか?
以下の表は、過去の通関士試験の結果です。合格率が年によって大きく変動していることが分かります。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 備考(合格基準点の調整など) |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 (H28) | 6,997名 | 688名 | 9.8% | |
| 2017年 (H29) | 6,535名 | 1,392名 | 21.3% | |
| 2018年 (H30) | 6,218名 | 905名 | 14.6% | |
| 2019年 (R1) | 6,388名 | 878名 | 13.7% | |
| 2020年 (R2) | 6,745名 | 1,140名 | 16.9% | |
| 2021年 (R3) | 6,961名 | 1,097名 | 15.8% | |
| 2022年 (R4) | 6,336名 | 1,212名 | 19.1% | |
| 2023年 (R5) | 6,332名 | 1,534名 | 24.2% | 近年で最も高い合格率 |
| 2024年 (R6) | 6,135名 | 759名 | 12.4% | 「関税法等」の基準点が55%に引き下げ |
この変動は、単に試験問題の難易度が毎年違うというだけでなく、試験実施機関が合格率を一定の範囲内に収めようとする「調整弁」が働いている可能性を示唆しています。
「満点の60%」が原則。しかし例外(救済措置)もある
通関士試験の合格基準は、原則として「全3科目において、それぞれ満点の60%以上を得点すること」です。
しかし、これには重要な例外があります。特定の科目が著しく難化し、受験者全体の得点水準が低いと判断された場合、その科目の合格基準点が引き下げられることがあるのです。実際に昨年の試験では「関税法等」が55%に引き下げられました。
第59回試験の合格基準点(ボーダーライン)を大予想
上記の仕組みから考えると、合格の可能性を判断する上で重要なのは、絶対的な点数よりも「他の受験者と比較してどの位置にいるか」という相対的なパフォーマンスです。
もし、多くの受験者が「今年の関税法等は異常に難しかった」と感じていれば、基準点が引き下げられる可能性は高まります。予備校の分析会などで専門家が「著しく難化した」との見解を示した場合、昨年と同様の措置が期待できるかもしれません。
自己採点で50%台後半だったとしても、決して諦めるのは早いのです。
自己採点の結果が出たら|3つのシナリオ別・次の一手
自己採点の結果をもとに、合格発表(令和7年11月11日(火))までの期間をどう過ごすべきか、3つのシナリオに分けて解説します。
シナリオ①:全科目60%超えで合格濃厚な方
おめでとうございます!まずは心と体をゆっくり休ませて、これまでの努力をねぎらってあげてください。
合格後のキャリアプランを考えたり、通関士登録までの手続きを調べ始めたりするのも良いでしょう。
シナリオ②:ボーダーライン上で結果が読めない方
最も落ち着かない期間を過ごすことになるかと思います。しかし、前述の通り、合格基準点の調整によって合格する可能性は十分にあります。
この期間は、無理に次の勉強を始めるよりも、予備校の分析会などに参加して情報を集め、冷静に結果を待つことをお勧めします。
シナリオ③:残念ながら再挑戦を決意した方
悔しい結果だったかもしれませんが、この試験で得た経験は決して無駄にはなりません。むしろ、今回の経験は次回の合格に向けた何よりの財産です。
なぜ点数が伸びなかったのか、学習方法に改善点はなかったかを客観的に振り返り、第60回試験に向けた新たな戦略を練る準備期間としましょう。早期にスタートを切ることで、来年の合格はぐっと近づきます。
具体的な学習戦略については、独学での合格を目指すための完全ガイドも参考にしてください。
早期にスタートを切ることが、来年の合格への鍵となります。
もし独学での学習に少しでも不安を感じるなら、次こそ合格を確実にするために、客観的な実績のある通信講座を検討するのも一つの有効な戦略です。
しかし、いざ講座を探し始めると「結局どれが自分に合うの?」と迷ってしまいますよね。
当サイトでは、主要な通信講座を「結局、自分にはどれが合うの?」という疑問に答える形で徹底比較した記事を用意しています。まずはこの記事で全体像を掴み、ご自身に合った最高の戦略パートナーを見つけてください。
まとめ:未来へ向けた新たなスタート
第59回通関士試験の受験、本当にお疲れ様でした。
試験直後は、結果が気になって落ち着かない日々が続くかと思います。まずは、本記事で紹介した予備校の解答速報や分析会を活用し、客観的な情報を集めることに集中してください。
そして、どんな結果であれ、この試験に挑戦した経験はあなたのキャリアにとって大きなプラスになります。
今回の経験を糧に、次の一歩へと進まれる皆様を心から応援しています。
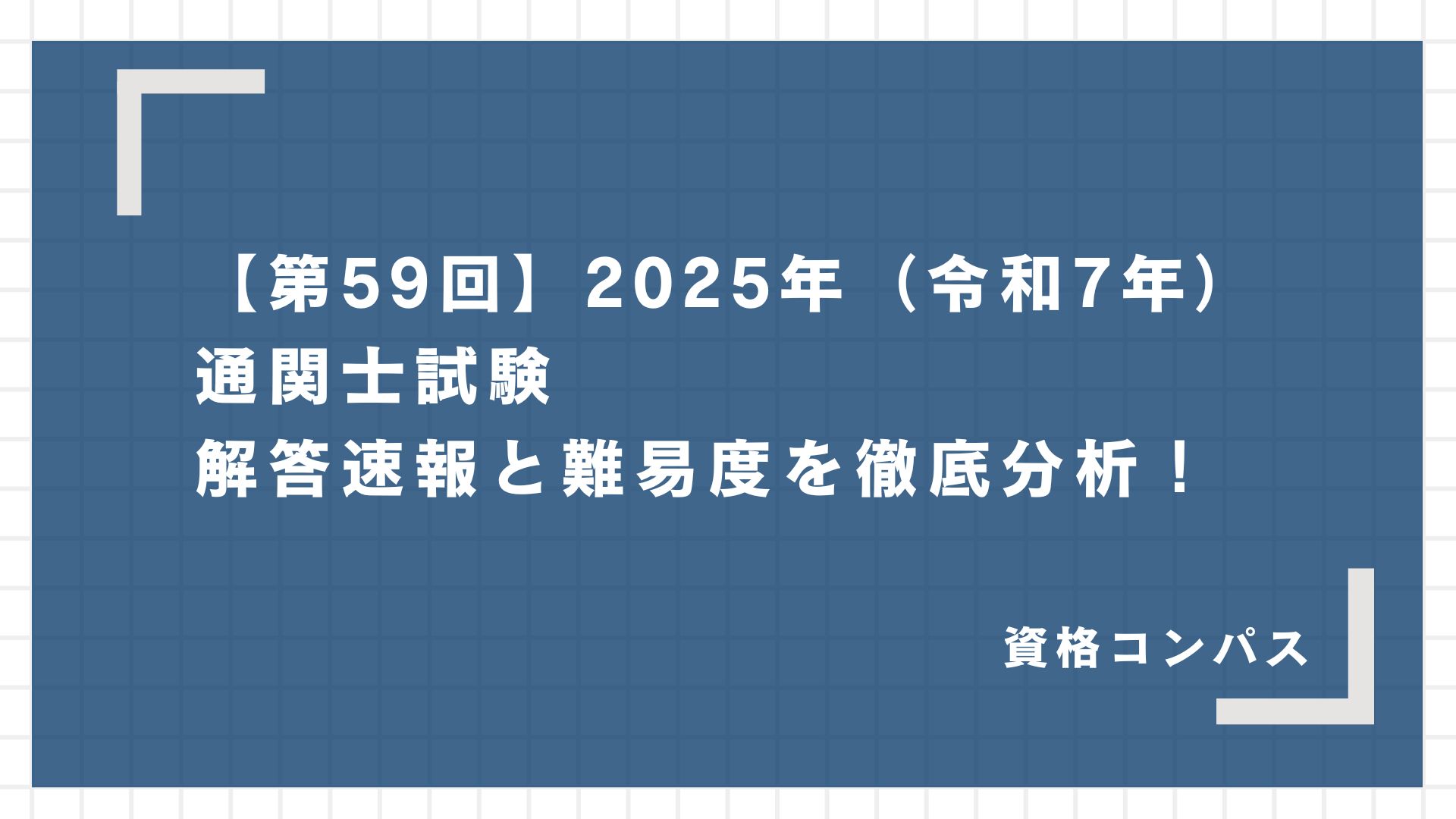




コメント