通関士試験の合格への羅針盤、「資格コンパス」へようこそ。
このシリーズでは、得点源にすべき戦略科目「通関業法」を条文ごとに分かりやすく解説しています。
前回の第1回では、通関業を始めるための「総則」と「許可」について学びました。今回はその続き、許可を得た後の具体的な業務ルールと、通関のプロフェッショナルである「通関士」個人の役割と義務に焦点を当てていきます。
今回の解説では、単なる原則だけでなく、試験で頻繁に問われる「例外規定」や、その背後にある法律の考え方まで一歩踏み込んで解説します。
▼通関業法の全体像と学習のポイントは、こちらの完全攻略ガイドで解説しています。
通関業者の義務 – 専門家による業務運営の担保
通関業法は、まず専門家が営業所に「存在する」こと(設置義務)を定め、その上で、その専門家が果たすべき中核的「機能」(審査・記名義務)を規定するという、論理的な構造になっています。この流れで理解していきましょう。
第13条(通関士の設置) – 専門家の配置義務
通関業の品質と適正さを担保するための最も重要なルールが、この「通関士の設置義務」です。原則として、すべての営業所に最低1名は通関士を配置する必要があります。
【試験のポイント:例外規定(ただし書き)の存在】
しかし、この原則には極めて重要な例外があります。法律の条文(ただし書き)で、通関士を置かなくてもよいケースが定められています。
例外が適用されるケース
取り扱う貨物が「一定の種類の貨物のみ」に限られている営業所
これは、業務範囲が限定的で、手続きが定型化・反復的になるような営業所を想定したものです。法律は、業務の複雑性やリスクが低い場合には、規制を合理化するという柔軟な姿勢(リスクベースのアプローチ)をとっており、この「例外」こそが試験で問われやすいのです。「全ての営業所に必ず必要」という覚え方では対応できないため、注意しましょう。
第14条(通関書類の審査・記名) – 専門家によるチェック機能
設置された通関士の最も重要な役割が、重要書類の審査と記名です。
【一歩進んだ理解:なぜこれらの書類なのか?】
通関士の審査・記名が必要な書類は、通関業法施行令第6条で定められています。なぜこれらの書類が選ばれているのか、その共通点を理解すると記憶に定着しやすくなります。
- 関税額の確定に直接影響を与える書類(金銭的リスクが高い)
- 輸出入申告書、特例申告書、修正申告書、更正請求書など
- 税関の行政処分に対する法的な異議申し立て書類(法的紛争性が高い)
- 不服申立書(審査請求書など)
つまり、法律は専門家のリソースを「納税額の確定」と「法的紛争」という、最も重要かつリスクの高い場面に集中させているのです。
第20条(信用失墜行為の禁止) – 高度な職業倫理
通関業は公共性の高いビジネスであるため、重い職業倫理が課せられています。
【条文のポイント】
通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
この規定の対象は、一般的な「従業員」は含まれません。事業許可を受けた「通関業者(役員含む)」と、国家資格を持つ「通関士」という二つの主体に限定されています。これにより、組織としての責任と、個人の専門家としての責任という「二重の責任構造」が法的に確立されているのです。
通関士の役割と義務 – 個人の資格者としてのルール
ここからは、「通関士」という個人の資格者に課せられたルールを見ていきましょう。
第31条(通関士の資格と確認) – 通関士になるための最終ステップ
通関士として働くには、(1)試験合格、(2)欠格事由非該当、(3)税関長の確認、という3つのステップが必要です。
【豆知識:「財務大臣」と「税関長」の関係】
実は、通関業法の条文上、確認の権限を持つのは「財務大臣」と定められています。しかし、実務の窓口は「税関長」です。
これは「権限の委任」という行政法上の仕組みによるものです。法律は最終的な権限を国の大臣に与えつつ、実際の運用は下位法令(政令)によって、現場である各地域の税関長に任せているのです。この法の運用メカニズムを知っておくと、法体系の理解が深まります。
第33条(名義貸しの禁止) – 資格を他人に貸さない
通関士は、自己の名義で他人に通関業務を行わせてはなりません。
【試験のポイント:適用範囲の拡張(括弧書き)に注意!】
この条文には、試験で狙われやすい重要な「括弧書き」があります。
名義貸し禁止の対象者
通関士(前条第一号の規定に該当し、第二十二条第二項の規定による異動の届出がない者を含む。)
これは、通関士が退職などで業務に従事しなくなった後でも、その旨の「異動届」が税関に提出されるまでの間は、引き続き名義貸し禁止の義務を負うことを意味します。
税関の公的記録が変更されるまで、専門家としての義務は「残存する」という、資格の厳格な管理を示す非常に重要な規定です。
まとめ:業務と通関士の役割を正確に理解しよう
今回は、許可を得た後の具体的な業務ルールと、通関士個人の義務について、試験で問われる例外規定まで含めて解説しました。
- 通関業者の義務
- 営業所ごとに通関士を設置する(第13条)。ただし、特定の貨物のみを扱う営業所の例外あり。
- 施行令で定める重要書類(輸出入申告書など)は、通関士に審査・記名させる(第14条)。
- 信用失墜行為の禁止。対象は通関業者(役員含む)と通関士(第20条)。
- 通関士個人の義務
- 試験合格後、税関長の「確認」を受ける(第31条)。権限は財務大臣から委任されている。
- 名義貸しをしてはならない(第33条)。退職後も異動届提出までは義務が残存する。
学習を深めるために:一次情報源の活用
本ブログのような解説記事は、複雑な法律を理解するための良い出発点です。しかし、最終的に最も信頼できるのは、法律の条文そのものです。
学習中に疑問点や不明点が出てきた際は、政府の公式な法令データベースである「e-Gov法令検索」で原文を確認する習慣をつけましょう。これが、合格を確実にするための最善の方法です。
次回は、許可内容に変更があった場合などの「営業・届出」に関するルールについて解説していきます。
この記事が、あなたの合格への羅針盤となることを願っています。
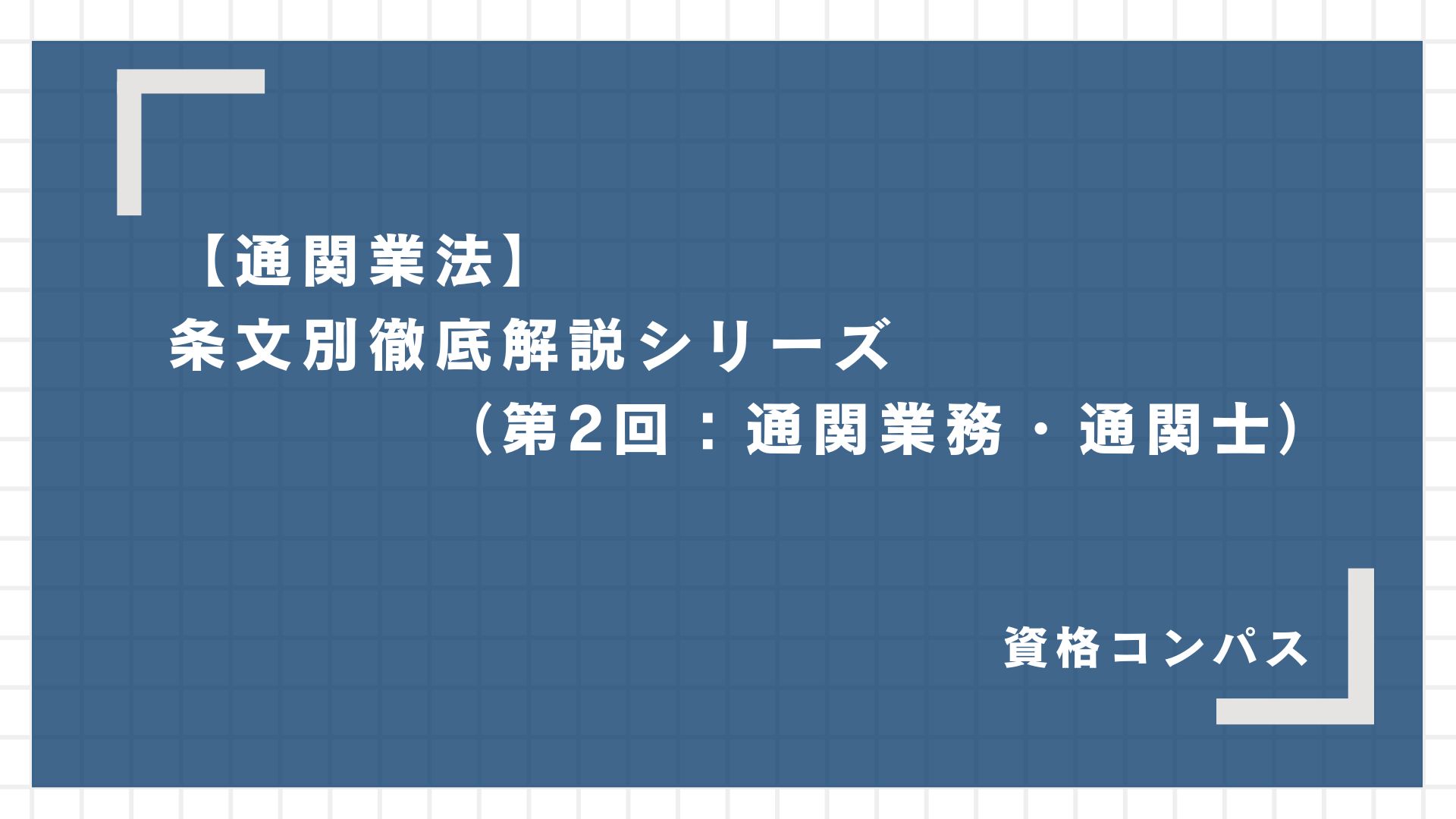





コメント