通関士試験の合格への羅針盤、「資格コンパス」へようこそ。
このシリーズでは、得点源にすべき戦略科目「通関業法」を条文ごとに分かりやすく解説しています。
第1回で「許可」、第2回で「通関業務と通関士の義務」を学びました。今回は、事業を開始した後の日常的な営業ルールと、何らかの変更があった際の「届出」の義務について解説します。
単なるルールの暗記ではなく、なぜそのようなルールがあるのかという背景まで理解することで、知識はより確実なものになります。
▼通関業法の全体像と学習のポイントは、こちらの完全攻略ガイドで解説しています。
営業所におけるルール – オフィスで守るべきこと
通関業者の営業所では、クライアント(依頼者)の保護や業務の記録保持のため、法律で定められたルールを守る必要があります。
第18条(料金の掲示)- 透明性の確保
通関業者がクライアントから受け取る料金(通関業務の報酬)は、自由に設定できます。しかし、その料金体系は誰にでも分かるように明示しておかなければなりません。
【条文のポイント】
通関業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、その料金の額を掲示しなければならない。(根拠:通関業法 第18条)
【なぜ?】本規定の目的
この規定は、専門家と依頼者の間にある情報の格差を是正し、依頼者を保護するためのものです。料金の透明性を確保することで、不当に高額な請求を防ぎ、公正な市場競争を促す目的があります。
第22条(帳簿の備付け)- 取引記録の保存義務
通関業者は、取り扱った通関業務について、その内容を記録した帳簿を作成し、関連書類と共に保存する義務があります。
【条文のポイント】
- 通関業者は、政令で定めるところにより、その通関業務に関して帳簿を設け…なければならない。(根拠:通関業法 第22条第1項)
- 当該帳簿は、閉鎖の後3年間保存しなければならない。
【試験のポイント:法階層の理解】
この「3年間」という具体的な保存期間は、法律(通関業法)には書かれていません。
- 法律(通関業法 第22条):帳簿の作成と「一定期間保存」という義務の原則を定める。
- 政令(通関業法施行令):法律の委任を受け、「3年」という具体的な期間を定める。
この「法律」と「政令」の役割分担(委任立法)は、試験で問われる重要な法体系の知識です。
【学習戦略アドバイス】
通関業法には「政令で定めるところにより」という表現が頻出します。これは、試験で問われる具体的な数字や手続きの多くが、法律そのものではなく、通関業法施行令などの下位法令に定められていることを示す重要なシグナルです。法律と政令をセットで学習することが合格への鍵となります。
届出の義務 – 変更があったときの手続き
事業を運営していると、様々な変更が生じます。その際には、定められた手続きに従って、監督官庁に報告する義務があります。
【法学上の基本用語】許可・消滅・届出とは?
手続きを理解する前に、言葉の意味を正確に押さえましょう。
- 許可 (Permission):行政庁が審査の上で、特定の活動を行う権利を与える承認行為。
- 消滅 (Extinction):廃業や死亡など、特定の事実の発生により、許可の効力が自動的に失われること。
- 届出 (Notification):特定の事実が発生したことを、行政庁に報告する行為。承認は不要。
営業所の新設と廃止
事業を拡大して営業所を増やしたり、逆に縮小して減らしたりする場合の手続きです。
- 営業所を新設する場合 → 財務大臣の「許可」が必要。(根拠:通関業法 第8条)
- 営業所を廃止する場合 → 以下の2段階のプロセスを正確に理解する必要があります。
- 許可の消滅(第10条):まず、営業所を廃止したという事実により、その営業所に対する通関業の許可が法的に「消滅」します。
- 届出(第12条):許可が消滅した結果として、その旨を遅滞なく財務大臣に「届け出る」義務が発生します。
「届出」は、許可が消滅したという事実を事後的に報告する手続きであり、原因(許可の消滅)と結果(届出義務)の関係性を正しく理解することが重要です。
変更事項の届出 – 第12条と第22条の役割分担
変更事項の届出は、その内容によって根拠となる条文が異なります。この二つの条文の役割分担は、試験の最重要ポイントです。
第12条(変更等の届出)- 許可名義人の根幹情報の変更
第12条は、「誰に許可を与えているのか」という、許可の主体そのものに関する情報の変更を管理するための規定です。
【届出が必要な主な事項(第12条)】
- 通関業者の氏名・名称及び住所の変更
- 役員の氏名・住所の変更
これらは、許可を与えた相手方の同一性と適格性を特定するための基礎情報であり、変更があった場合は遅滞なく届け出る必要があります。
第22条(届出事項)- 業務遂行体制(通関士等)の変更
第22条は、「どのように業務を遂行しているのか」という、日々の業務運営体制を管理するための規定です。
【届出が必要な主な事項(第22条)】
- 通関士その他の通関業務の従業者の氏名とその異動(配置、退職など)
行政庁は、どの営業所にどの有資格者が配置されているかを把握し監督する必要があるため、これらの変更についても遅滞なく届け出る必要があります。
まとめ:地味でも重要な営業・届出ルールをマスターしよう
今回は、日常業務に関わる営業ルールと、変更時の届出について解説しました。
- 営業所のルール
- 料金の掲示義務(第18条)。目的は依頼者の保護。
- 帳簿の備付け義務(第22条)。保存期間3年は政令で規定。
- 届出の義務
- 営業所の新設は「許可」(第8条)。
- 営業所の廃止は、許可の消滅(第10条)に伴い、「届出」が必要(第12条)。
- 名称や役員の変更は第12条に基づき「届出」。
- 通関士や従業者の異動は第22条に基づき「届出」。
数字や手続き、そしてその根拠条文の違いは、試験で格好の出題ポイントとなります。一つひとつ正確に記憶していきましょう。
次回は、通関業者が不正を犯した場合などに課せられる「監督・懲戒」に関する条文を解説します。
この記事が、あなたの合格への羅針盤となることを願っています。
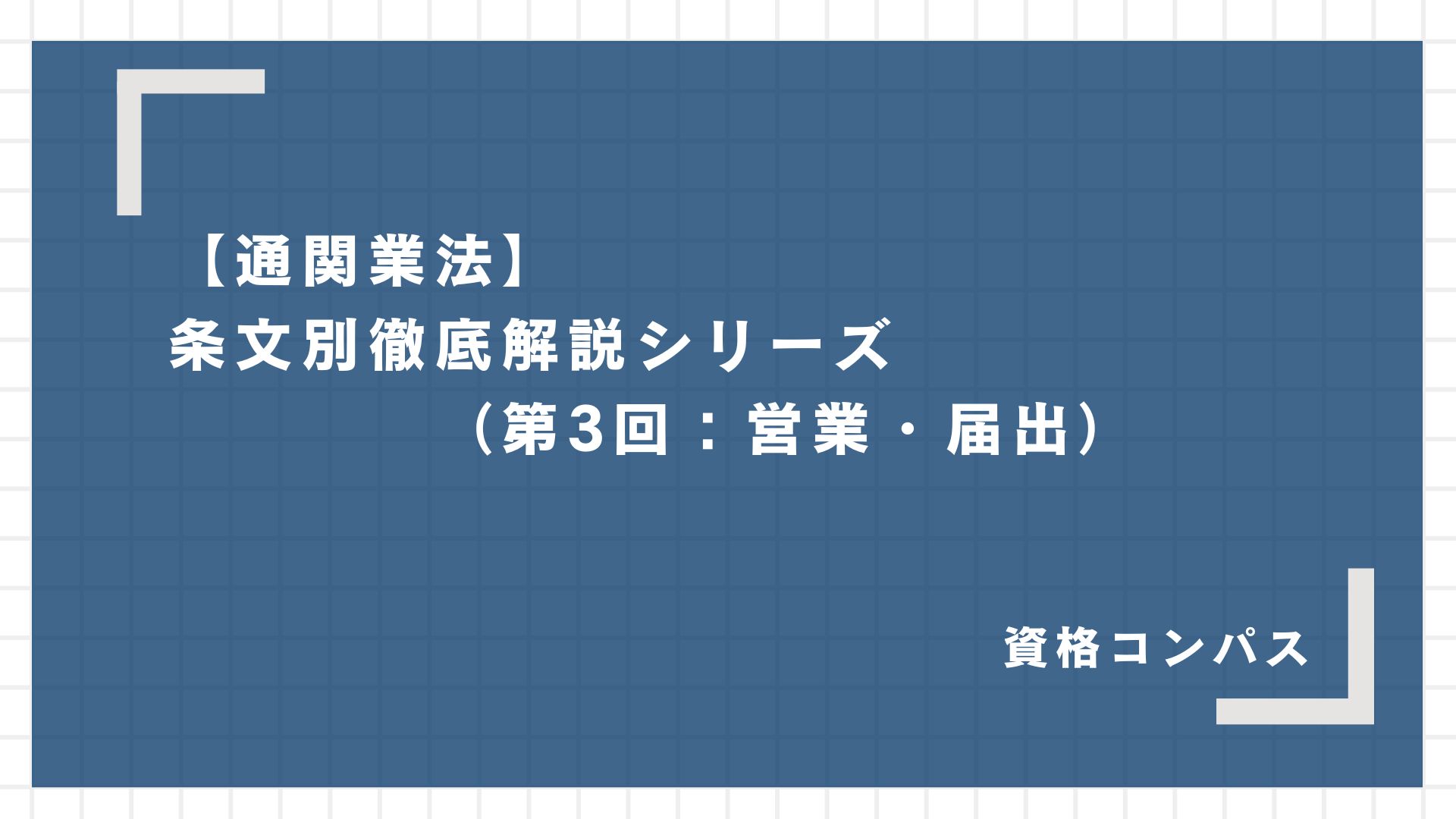





コメント