通関士試験の合格への羅針盤、「資格コンパス」へようこそ。
このシリーズでは、得点源にすべき戦略科目「通関業法」を条文ごとに分かりやすく解説しています。
これまで、事業の「許可」、許可後の「業務ルール」、そして「営業・届出」について学んできました。今回は、法律で定められたルールが守られなかった場合に何が起こるのか、すなわち「監督処分」と「懲戒処分」について解説します。
この分野は2017年に重要な法改正が行われており、古い情報では対応できません。処分の種類や対象、権限者を正確に区別して覚えることが、合格への鍵となります。
▼通関業法の全体像と学習のポイントは、こちらの完全攻略ガイドで解説しています。
通関業者に対する監督処分 – 事業者へのペナルティ
まず、会社や個人事業主である「通関業者」が法令に違反した場合に科される監督処分です。処分を行う権限は財務大臣にあります。
第33条の2(業務改善命令)- 予防的是正措置
現行法における最も軽微な監督処分です。以前は「戒告」という処分がありましたが、2017年の法改正で廃止され、より実効的なこの制度が導入されました。
【条文のポイント】
財務大臣は、通関業者の業務の運営に関し改善が必要であると認めるとき、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
単なる注意ではなく、具体的な改善策の実行を法的に命じるもので、将来の違反を予防・是正することを目的としています。
第34条(監督処分)- 業務停止と許可の取消し
違反の程度が重い場合には、事業の継続に直接影響する、以下の重い処分が下されます。
- 一年以内の期間を定めて通関業務の全部又は一部の停止
最大1年間の営業停止命令です。事業の継続に重大な支障をきたす、非常に重い処分です。 - 許可の取消し
最も重い処分で、通関業の許可そのものを取り消される、いわば「死刑宣告」です。一度許可を取り消されると、その日から2年間は新たに許可を受けることができなくなります(欠格事由)。
通関士に対する懲戒処分 – 個人の資格者へのペナルティ
次に、国家資格者である「通関士」個人が義務違反などをした場合に科される懲戒処分です。処分を行う権限は、同じく財務大臣です。
第35条(懲戒処分)- 個人への3段階の処分
通関士に対する懲戒処分は、以下の3段階です。
- 戒告
最も軽い処分で、将来を戒める旨の公式な注意・警告です。 - 一年以内の期間を定めて通関業務に従事することの停止
通関士として働くことを、最大1年間禁止される処分です。 - 二年間の通関業務に従事することの禁止
これが通関士個人に対する最も重い懲戒処分です。
「失格」ではない! – 最重処分の正しい理解【最重要】
古いテキストなどでは、最も重い処分を「失格」と表現している場合がありますが、これは完全な誤りです。
【試験のポイント】
- 通関業法第35条に「失格」という言葉はありません。
- 最も重い処分は、あくまで「二年間の通関業務に従事することの禁止」という有期の処分です。
- 永久に資格を失うわけではありません。 2年の禁止期間が満了した後、改めて第31条に基づく財務大臣の「確認」を受ければ、再び通関士として働くことが法的に可能です。
この規定の背景には、過ちを犯した専門家を社会から完全に排除するのではなく、一定の制裁期間を経た上での更生の機会を与えるという法の理念があります。
まとめ:【2017年法改正対応】監督・懲戒処分の正確な比較表
監督処分と懲戒処分は、権限者がどちらも財務大臣であるなど共通点もありますが、その違い、特に処分の種類を正確に覚えることが不可欠です。
| 項目 | 監督処分 | 懲戒処分 |
|---|---|---|
| 対象 | 通関業者(事業者) | 通関士(個人資格者) |
| 権限者 | 財務大臣 | 財務大臣 |
| 最も軽微な処分 | 業務改善命令 | 戒告 |
| 中間の処分 | 1年以内の業務停止 | 1年以内の業務従事停止 |
| 最も重い処分 | 許可の取消し | 二年間の業務従事禁止 |
| 最重処分の効果 | 新規許可の欠格事由(2年間) | 通関士の確認の欠格事由(2年間)。期間満了後、再度の「確認」により復職可能 |
次回は、通関業法シリーズの最終回として、これまで見てきた行政罰とは異なる「刑事罰」を定めた「罰則」規定などを解説します。
この記事が、あなたの合格への羅針盤となることを願っています。
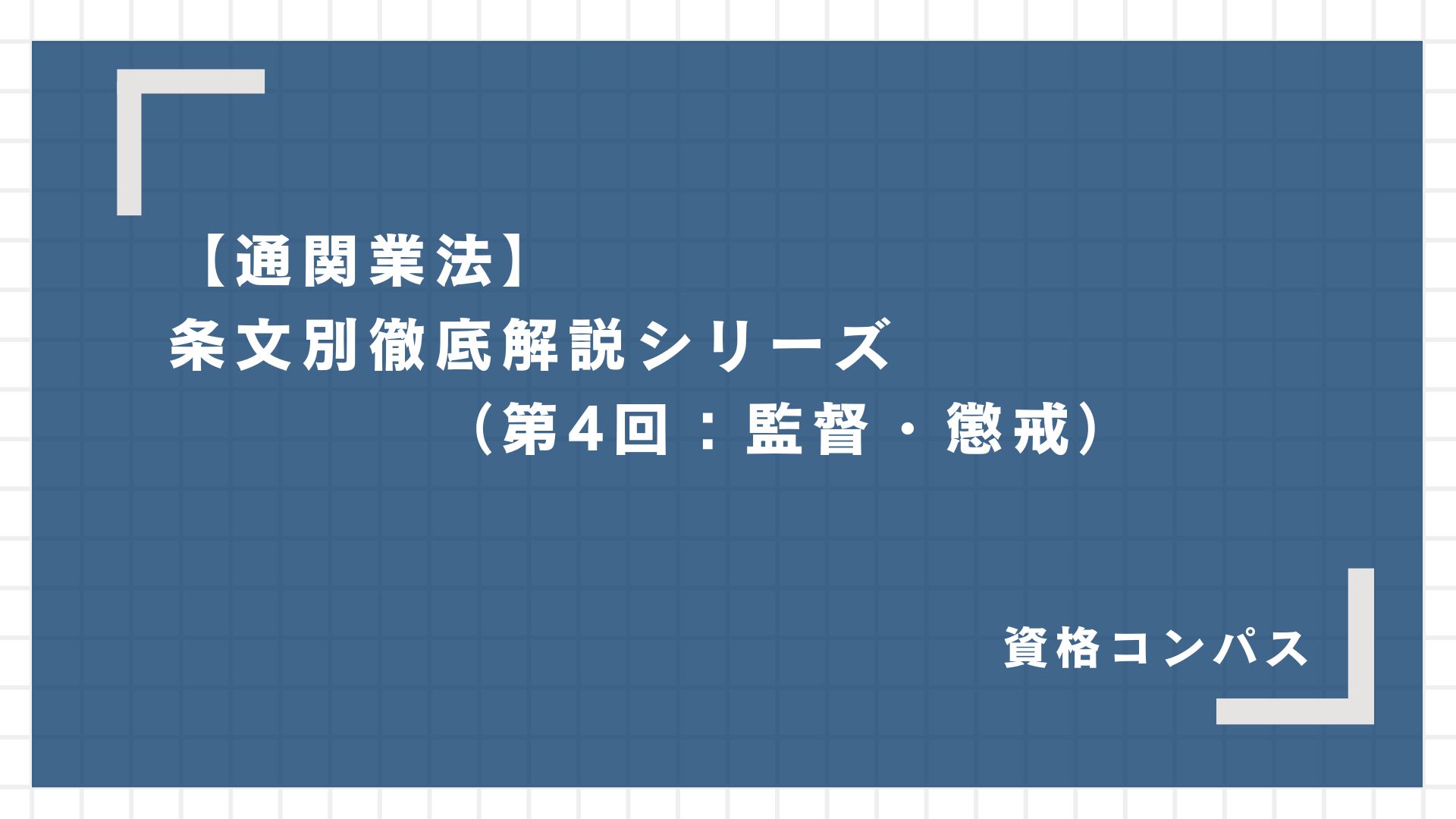





コメント