海外のオンラインショップで気軽に買い物をする。多くの人にとって当たり前になったこの行動の裏側で、日本の税制と国際物流の根幹を揺るがす、大きな構造変化が静かに、しかし確実に進行しています。
その中心にあるのが、「課税価格1万円以下の貨物の関税・消費税を免税とする」という、いわゆる少額輸入貨物の免税制度(デミニミス制度)です。
この制度が、越境EC(海外ネット通販)の爆発的な拡大という現実に、もはや対応しきれなくなっているのです。2023年には、日本の総輸入許可件数約1億9,000万件のうち、実に約9割にあたる約1億7,000万件がこの免税制度の対象となる少額貨物で占められるという異常事態に至りました。この問題に対応するため、財務省は2025年6月に専門家によるワーキンググループ(WG)を設置し、本格的な議論を開始しました。
この記事は、単なるニュース解説ではありません。財務省が提示する公式データと海外の先行事例を基に、この制度が将来どのように変わる可能性が高いのか、そしてその変化が、未来の通関士の仕事にどのような本質的な変革をもたらすのかを、専門的な視点から深く予測・考察します。
結論:制度見直しは不可避。焦点は「プラットフォーム事業者課税」への移行
最初に結論を述べます。少額輸入貨物に対する免税制度の抜本的な見直しは、もはや不可避です。
現在の制度が抱える「課税の公平性」や「安全保障上のリスク」といった課題は、すでに許容範囲を超えています。世界的な潮流を見ても、同様の免税制度を維持している先進国は少数派となりつつあります。
したがって、我々が注目すべきは「見直されるかどうか」ではなく、「いつ、どのような方法で変更されるのか」という一点に尽きます。そして、その最も有力な選択肢は、EUやオーストラリアが先行導入している「プラットフォーム事業者課税方式」です。これは、海外ECプラットフォーム事業者に納税義務を課すモデルであり、この変更は、通関士という専門職の役割を再定義するほどのインパクトを秘めています。
現行制度の基本と「3つの構造的欠陥」
未来を予測するためには、まず現状を正確に理解する必要があります。
まずは基本の確認:少額輸入貨物免税制度とは?
この制度は、主に以下の2つのルールから成り立っています。
- 少額貨物の免税: 一つの輸入申告における貨物の課税価格の合計額が1万円以下の場合、原則として関税及び輸入消費税が免除されます。
- 個人輸入の特例: 個人が私的に使用する目的で商品を輸入する場合、課税価格は海外の小売価格の60%として計算されます。
この2つのルールを組み合わせると、海外の小売価格が16,666円までであれば、免税の対象となるわけです(16,666円 × 0.6 ≒ 1万円)。
ただし、革製品やニット製衣類、履物など、国内産業保護の観点から一部適用除外品目が定められています。
▼ この制度の詳しいルールや適用除外品目については、こちらの記事で解説しています。
なぜ今、見直しなのか?制度が抱える3つの構造的欠陥
この制度は、個人間の贈答品や少量のサンプルなどを想定して作られたものですが、現代のビジネス環境との間に、無視できない「3つの構造的欠陥」を生み出しています。
欠陥①:越境ECによる物理的飽和(規模の歪み)
最大の要因は、越境ECプラットフォームの台頭による、少額貨物の爆発的な増加です。前述の通り、2023年には少額貨物の許可件数が約1億7,000万件に達し、前年比で約35%も増加しました。これは制度が想定していた規模を遥かに超える物理的な飽和状態です。
欠陥②:国内外の事業者間における「課税の公平性」の喪失(競争の歪み)
もしあなたが国内で8,000円の商品を売れば、消費税を上乗せして納税する義務があります。しかし、海外の事業者が同じ商品を日本の消費者に売る場合、免税制度によって消費税が課されません。
これは、国内で真面目に税金を納めている事業者が、価格競争上、著しく不利な状況に置かれていることを意味し、政府税制調査会でも「イコールフッティング(equal footing)」の観点から問題視されています。
欠陥③:水際取締りの限界と安全保障上のリスク(安全の歪み)
年間1億7,000万件もの小口貨物一つひとつを、税関がすべて開封して検査することは物理的に不可能です。
この状況を悪用し、知的財産権侵害物品(偽ブランド品)や、不正薬物がこのルートを通じて国内に流入するリスクが急増しています。事実、2023年の知的財産侵害物品の輸入差止件数は過去最多の3万3,000件超を記録し、不正薬物の摘発も後を絶ちません。これは、国民の安全や経済秩序を守るという、税関本来の役割を揺るがす重大な問題です。
世界の潮流と日本の進む道
この問題は日本特有のものではなく、世界各国がすでに対策を講じています。
世界はどう動いているか?- EU・オーストラリアの先行事例
- EU: 2021年に、それまで22ユーロ未満の輸入品に適用されていたVAT(付加価値税)の免税措置を完全に撤廃しました。
- オーストラリア: 2018年に、1,000豪ドル以下の輸入品に対するGST(物品サービス税)の免税措置を撤廃しました。
これらの国で共通しているのは、免税基準をなくし、海外のECプラットフォーム事業者自身に、販売時点で現地の消費税を徴収・納税する義務を課したことです。これにより、徴税のタイミングを「国境」から「販売時点」へと前倒しし、税関の負担を軽減しています。
財務省のワーキングループでは、日本の税関の処理能力を考慮すると、EUのモデルよりも、一定規模以上の事業者に登録を義務付けるオーストラリアのモデルが、より現実的な選択肢として議論されています。
【未来予測】通関士の仕事はどう変わるか?
これらの背景と国際動向を踏まえると、日本も「免税基準額の撤廃」と「プラットフォーム事業者への納税義務化」へと進む可能性が極めて高いと予測されます。その時、通関士の仕事はどのように変わるのでしょうか。
予測①:定型的な少額貨物申告業務の価値が低下する
現在、急増する越境EC貨物の多くは、クーリエなどがシステムを利用して大量に、かつ効率的に処理しています。仮に免税制度が撤廃されても、この「大量処理」の構造自体は変わらないでしょう。むしろ、納税手続きのシステム化はさらに加速し、この分野における人間(通関士)の定型的な事務作業の価値は相対的に低下します。
予測②:「データアナリスト」としての役割が生まれる
免税制度が見直されれば、これまで十分に捕捉できていなかった、膨大な数の消費者向け取引データが新たに生まれます。AEO事業者や大手通関業者に所属する通関士には、これらのビッグデータを分析し、リスク管理やコンプライアンス上の傾向を把握する、データアナリストに近い役割が求められるようになります。統計学の知識やBIツールを使いこなし、データから不正の兆候を掴んだり、サプライチェーンの最適化を提案したりする能力が重要になるでしょう。
予測③:「戦略的コンプライアンス・コンサルタント」への進化
制度が複雑化すればするほど、専門家による助言の価値は高まります。
「この取引形態の場合、納税義務者は誰になるのか」「新しいシステムに、自社の業務フローをどう適応させるべきか」「税関ではなく国税庁の事後調査にどう備えるか」といった、高度なコンプライアンス体制の構築や、業務改善に関するコンサルティングが、通関士の新たな収益源となり得ます。これは、AIには決して代替できない、法律・税務・IT・物流の知識を融合させた、人間の専門家ならではの領域です。
まとめ:変化を先読みする専門家へ
今回の分析をまとめます。
- 現状: 少額輸入貨物免税制度は、越境ECの拡大により「規模・競争・安全」の3つの面で構造的な欠陥を抱えています。
- 世界の潮流: EUなどが先行して免税措置を撤廃し、ECプラットフォームに納税義務を課すモデルへ移行済みです。
- 未来予測: 日本も制度見直しは必至であり、豪州モデルを参考にする可能性が高い。これにより、通関士の仕事は、定型的な事務作業から、データ分析や高度なコンサルティングといった、より付加価値の高い業務へとシフトしていくでしょう。
この変化は、決して悲観するべきものではありません。むしろ、社会の要請に応え、通関士が単なる「手続き代行者」から、国際物流とコンプライアンスを支える真の「戦略的パートナー」へと進化する絶好の機会と捉えるべきです。
このような業界の未来を先読みし、自らのスキルを磨き続ける姿勢こそが、これからの時代に求められる専門家の姿と言えるでしょう。
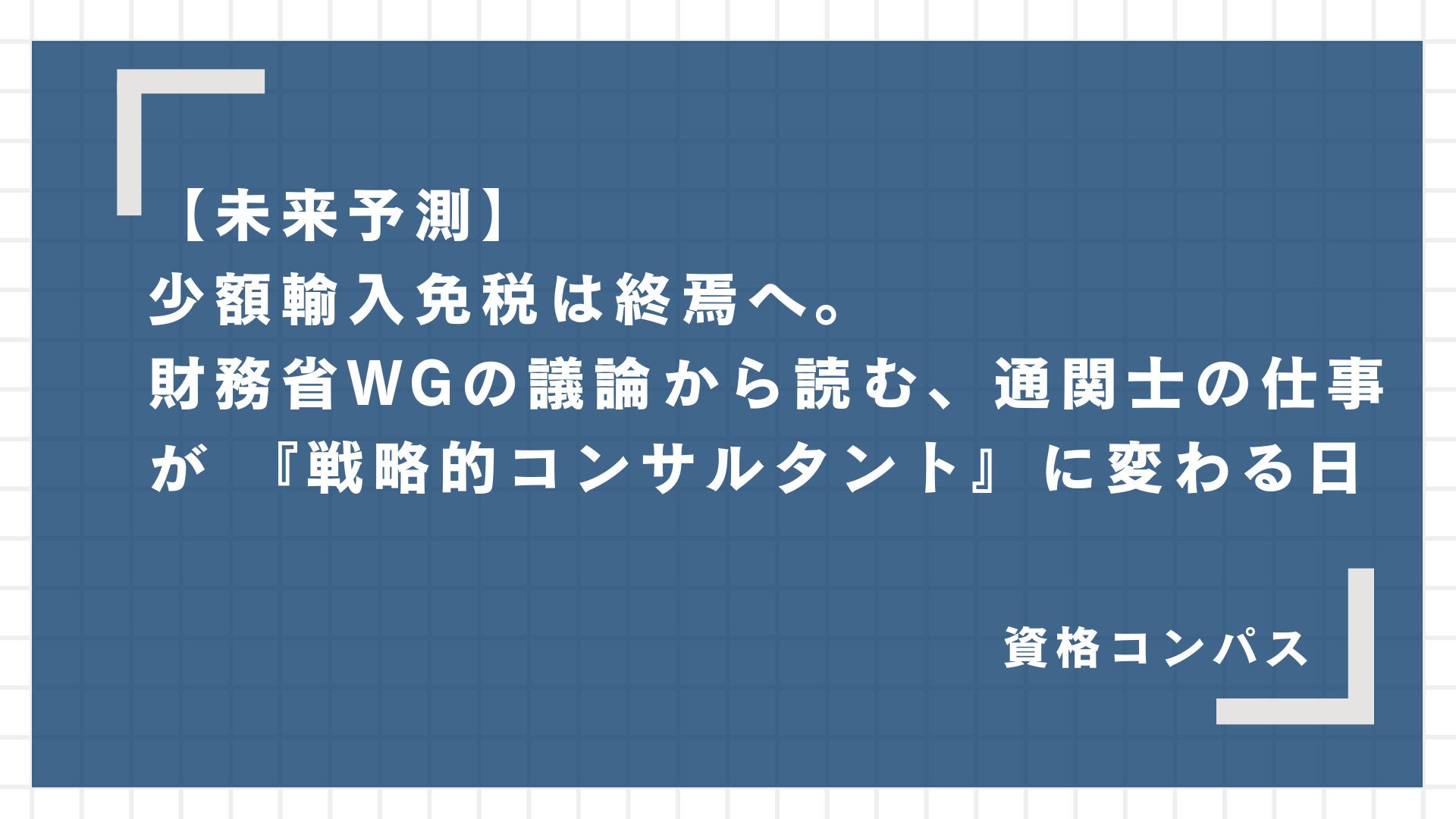



コメント