「関税法等の暗記量が多すぎて、全然覚えられない…」
「複雑な法律の条文、何かラクに覚える方法はないの?」
通関士試験の最重要科目「関税法等」。この科目の攻略は、まさに暗記との戦いです。しかし、力任せの暗記は、不合格への最短ルートかもしれません。
この記事では、脳科学の知見に基づき、あなたの暗記の負担を劇的に軽減する効率的な記憶術を伝授します。さらに、巷で語られる語呂合わせの危険な落とし穴と、それを安全に活用する方法も徹底解説します。
この記事を読めば、あなたは暗記に対する苦手意識を克服し、「関税法等」を得意科目に変えることができるでしょう。
戦略の前提:記憶術は「理解」の補助ツールである
いかなる記憶術を用いるにせよ、大前提は「まず法令の条文そのものを読み、その趣旨と論理を理解すること」です。理解という土台があって初めて、記憶術はその真価を発揮します。記憶術は、理解の代用品には決してなりません。
脳科学が教える!効率的な3つの記憶術
脳の仕組みを理解し、ハックすることで、学習効率は飛躍的に向上します。
1. チャンク化(情報を圧縮し、構造化する)
バラバラの情報を、意味のある3~4つの塊(チャンク)にまとめる手法です。脳が一度に意識的に処理できるチャンク数は約4つと言われており、この脳の限界を克服するために情報を圧縮・構造化します。
- ポイント: 最も重要なのは、完成したチャンクを覚えることではなく、情報の中から能動的にパターンを発見し、自ら論理的なグループを創造するという知的作業そのものです。このプロセスが、情報を長期記憶に定着させます。
【実践例:納税義務者の例外規定】
納税義務者の例外規定を単に羅列して覚えるのではなく、以下のように、自ら論理的なチャンク(グループ)を創造しましょう。
- 「場所」がトリガーになるグループ: 保税蔵置場に入れる、総合保税地域に置く など
- 「行為」がトリガーになるグループ: 許可された用途外に使用する など
- 「地位」によるグループ: 連帯納税義務者 など
2. 物語化記憶術(感情とイメージで符号化する)
文字情報を、感情を伴う鮮やかな物語として頭の中で創作するテクニックです。脳は文字より画像を記憶しやすく(画像優位性効果)、さらに感情を伴う出来事は記憶の中枢である「海馬」を刺激し、記憶を強固にします。
【実践例:「更正の請求期間が原則5年」】
「5年」と数字で覚えるのではなく、「申告ミスに青ざめた納税者が、5年間のタイムリミットが迫る中、必死で書類をかき集めて税関に駆け込み、安堵する」という短編映画を頭の中で創作します。登場人物の焦りや安堵といった感情が、記憶を忘れがたいものに変えます。
3. 身体を動かす(脳の学習環境を最適化する)
記憶を頭の中だけで完結させず、身体の動きと結びつけます。特に、学習効率を根本的に向上させる戦略として、身体運動が極めて有効です。
- 実践法: 最も集中したい学習セッションの約60~90分前に、20~30分程度の軽い有酸素運動(早歩きなど)を終える。
- 科学的根拠: 運動によって脳内で分泌されるBDNF(脳由来神経栄養因子)は「脳の肥料」とも呼ばれ、脳が学習に最適な化学的環境となり、学習効率が飛躍的に向上します。
【要注意】巷の語呂合わせ、その危険性を徹底解剖
語呂合わせは魅力的ですが、その多くは法的な正確性や網羅性を犠牲にしており、試験対策としては極めて危険です。ここでは、代表的な語呂合わせとその危険性を一つひとつ具体的に解説します。
1. 課税物件の確定時期(関税法第4条)
巷の語呂合わせ
「ホッとしてそう?入場前に優待券で特例承認!」
【分析と危険性】
この語呂合わせは、関税法第4条に定められた数多くの例外規定のうち、ごく一部を恣意的に抜き出したものに過ぎません。
- 致命的な欠落: 試験で頻出する「保税運送中に亡失した貨物」や「公売に付される貨物」「滅却された貨物」といった、極めて重要な例外規定が完全に抜け落ちています。
- 結論: この語呂合わせに頼ると、例外規定を問う問題には全く対応できず、致命的な知識の偏りが生じるため、使用は非常に危険です。
2. 輸入してはならない貨物(関税法第69条の11)
巷の語呂合わせ
「まあ、アヘンで偽札なんて、公安失格だ!」
【分析と危険性】
これは危険なほど不完全かつ不正確であり、絶対に使用すべきではありません。
- 致命的な欠落: 法で定められた13カテゴリーのうち、「銃砲」「爆発物」「火薬類」「化学兵器」「特定病原体」といった、国の安全保障に関わる最重要品目が全く含まれていません。
- 結論: この語呂合わせは、学習の助けにならないばかりか、受験者の知識基盤に意図せずして重大な「盲点」を作り出します。直ちに記憶から消去すべきです。
3. 更正の請求ができる期間(国税通則法第23条)
巷の語呂合わせ
「構成員は5人」
【分析と危険性】
原則である「5年以内」という点は正しいですが、より重要な例外規定の存在を覆い隠してしまいます。
- 致命的な欠落: 申告後に判決が出た場合などに適用される「後発的事由」による更正の請求という、重要な例外規定の知識が抜け落ちます。この場合の請求期間は「5年」ではなく「事由が生じた日の翌日から2ヶ月以内」です。
- 結論: 法律系の試験では、こうした例外規定こそが合否を分けます。この語呂合わせは、応用問題に対応できなくなるリスクをはらんでいます。
4. 通関業の許可の消滅・失効(通関業法第10条)
巷の語呂合わせ
「死亡で解散、はい、廃業」
【分析と危険性】
これも不完全であり、重要な事由が欠落しています。
- 致命的な欠落: 通関業法第10条が定める4つの消滅事由のうち、「破産手続開始の決定を受けたとき」という極めて重要な一つが完全に抜け落ちています。
- 結論: 法が定める4つの要件のうち、3つしかカバーできていません。試験対策としては不十分であり、失点に直結する可能性があります。
安全な記憶術を「自作」するための5ステップ
不確かな語呂合わせに頼るリスクを回避し、あなただけの安全な記憶術を構築しましょう。
- 一次情報の分解: e-Gov法令検索などを活用し、対象条文の全ての要件・例外・キーワードをリストアップします。
- 論理的構造化(チャンク化): リストアップした要素を、論理的な基準で3~4のグループに分類します。
- 網羅性の検証: 作成したチャンクとリストを、信頼できる基本テキストと照合し、欠落がないか徹底的に検証します。
- 個人的物語化: 検証済みの全ての要素を織り込んだ、あなた自身の経験や感情と結びつく鮮やかな物語を創作します。
- 実践的修正: 過去問を解く際に自作の記憶術を試し、想起に失敗する部分があれば、物語を改良し、より強力な記憶のフックを作ります。
結論:暗記を「知的探求」へと昇華させよう
「関税法等」は、確かに暗記量の多い科目です。しかし、それは思考停止の単純作業ではありません。
- 脳科学の原理を応用し、学習効率を最大化する。
- 安易な語呂合わせの危険性を理解し、頼らない。
- 「理解」を土台とし、自ら「安全な」記憶術を創造する。
真のコンピテンシーは、巧妙なトリックの習得によって得られるものではありません。それは、正確な理解という揺ぎない土台の上に、科学的に裏付けられ、かつ自らその信頼性を検証した記憶術を体系的に用いることで、初めて涵養されるものです。
あなたの学習を、単なる「暗記ゲーム」から、専門家としての能力を築き上げるための知的探求へと昇華させていきましょう。
関税法等の他の重要論点については、『頻出論点マスターシリーズ』で一つずつ解説しています。
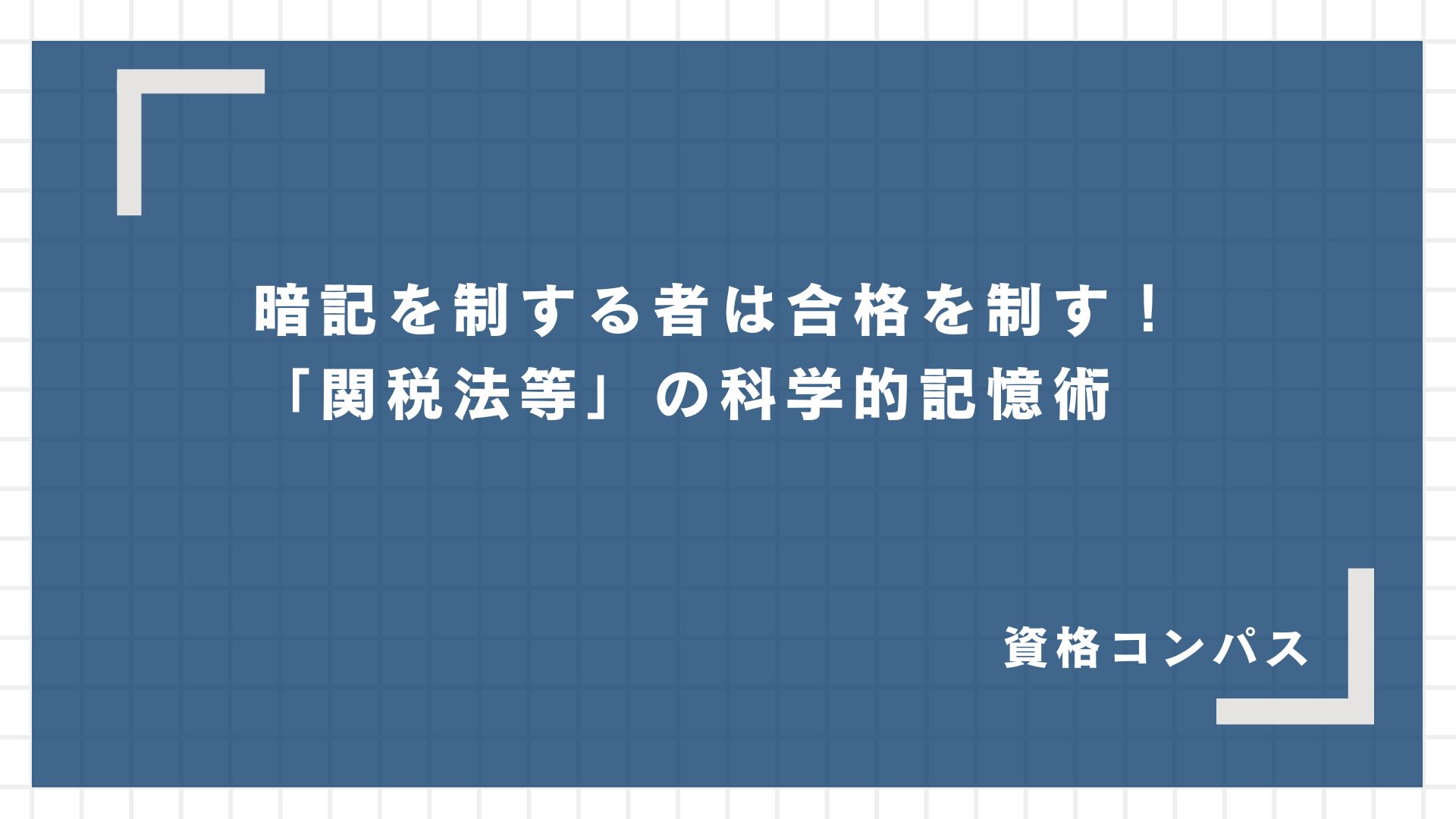
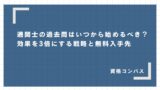
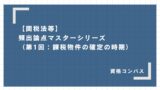



コメント