ようこそ、「資格コンパス」へ。このシリーズでは、通関士試験の難関科目「関税法等」の頻出論点を、一つずつ丁寧に解き明かしています。
前回の第2回では、「納税義務者」について、関税法と国税通則法を横断しながら、誰が納税の責任を負うのかを体系的に解説しました。
▼ 第2回の記事はこちら
さて、第3回のテーマは「特恵関税」です。
これは、特定の国の産品に対して、通常よりも低い関税率(または無税)を適用する特別な制度です。しかし、この制度は単純なものではありません。「一般特恵」と「LDC特別特恵」という二層構造になっており、さらにEPA(経済連携協定)との優先関係を理解することが、現代の貿易実務と試験対策の鍵となります。
特恵関税(GSP)とは? – 途上国を支援する「暫定的な」恩恵措置
特恵関税とは、開発途上国の経済成長を支援するために、先進国がそれらの国からの輸入品に対して、一方的に関税上の利益を与える制度です。二国間で相互の義務を負うEPAとは、この「一方性」において根本的に異なります。
制度の目的と法的根拠
この制度の国際的な枠組みはGSP(Generalized System of Preferences:一般特恵関税制度)と呼ばれます。日本では1971年から実施されており、そのルールは関税法ではなく、特別法である「関税暫定措置法」で定められています。
なぜ「暫定」なのでしょうか?それは、GSPが国際経済の状況に応じて柔軟に見直されるべき政策的・時限的な措置と位置づけられているためです(現在の適用期限は2030年度末まで)。
【最重要】一般特恵とLDC特別特恵
日本のGSPは、受益国の経済レベルに応じて二層構造になっています。
- 一般特恵: 政令で指定された特恵受益国・地域に適用される基本的な枠組みです。
- LDC特別特恵: 特恵受益国のうち、国連が特に開発の遅れた国と認定した「後発開発途上国(Least Developed Countries: LDC)」に対しては、一般特恵よりもさらに手厚い、原則として全ての品目が無税となる特別の優遇措置が適用されます。
【最重要改訂】GSPとEPA(経済連携協定)の優先関係
現代の貿易実務では、EPA税率とGSP税率のどちらを適用すべきか、という場面が頻繁に発生します。このルールは非常に複雑で、受益国がLDCか否かによって結論が異なります。
【LDCに対する最重要例外】
結論から言うと、LDC特別特恵受益国を原産地とする貨物については、常にGSP税率とEPA税率の有利な方を選択できます。
【一般特恵受益国へのルール】
一方、一般特恵受益国については、EPA税率がGSP税率と同じか、それより低い場合、GSPの適用が排除され、EPA税率しか選択できなくなります。これは、日本政府がより包括的なEPAの利用を促進する政策的意図の表れです。
GSP vs EPA 適用判断マトリクス
この複雑なルールを、以下のマトリクスで完全に整理しましょう。
| シナリオ | GSP税率 | EPA税率 | 一般特恵受益国への適用 | LDC特別特恵受益国への適用 |
|---|---|---|---|---|
| 1. GSPが有利 | 3% | 5% | GSP (3%) or EPA (5%) を選択可 | GSP (3%) or EPA (5%) を選択可 |
| 2. EPAが有利 | 5% | 3% | EPA (3%) のみ適用可(GSPは適用排除) | EPA (3%) or GSP (5%) を選択可 |
| 3. 税率が等しい | 3% | 3% | EPA (3%) のみ適用可(GSPは適用排除) | EPA (3%) or GSP (3%) を選択可 |
【試験の核心】特恵関税を受けるための3つの絶対条件
条件①:対象となる「国・地域」であること
特恵関税は、政令で指定された国・地域からの輸入に限定されます。
- 対象国(2024年5月現在): 特恵受益国は126か国・4地域、そのうちLDC特別特恵の対象は44か国です。
- 注意: このリストは毎年4月1日に見直される可能性があるため、常に税関のウェブサイトで最新の情報を確認する習慣が不可欠です。
- 卒業制度: 経済が発展した国は対象から外れます。2019年に中国、メキシコ、ブラジル、タイ、マレーシアが卒業したことは、非常に重要な出来事です。
条件②:対象となる「品目」であること
受益国からの輸入でも、全ての品目が対象となるわけではありません。
| 受益国区分 | 農水産品(HSコード第1-24類) | 鉱工業産品(HSコード第25-97類) |
|---|---|---|
| 一般特恵受益国 | ポジティブ・リスト方式: 政令で指定された品目のみが対象。 | ネガティブ・リスト方式: 一部除外品目(皮革製品等)を除く、原則全ての品目が特恵待遇(無税または減税)の対象。 |
| LDC特別特恵受益国 | 原則無税: ごく少数の例外を除き、全ての品目が無税。 | 原則無税: ごく少数の例外を除き、全ての品目が無税。 |
条件③:「原産地」と「輸送」の要件を満たすこと
1. 原産地基準の法的定義
貨物が特恵受益国の「原産品」であると認められるためのルールです。
- 完全生産品: その国で採れた鉱物や、収穫された農産物のように、完全にその一国のみで生産された産品。
- 実質的変更基準: GSPの主たる原則は「関税分類変更基準」です。完成品のHSコードの上4桁が、その生産に使用された全ての非原産材料のHSコードの上4桁と異なることを要求する客観的な基準です。
2. 運送要件の法的定義
原則として、貨物は原産地から日本へ直接輸送されなければなりません(直送原則)。
- 例外: 第三国を経由することは認められますが、その国で積替えや一時蔵置以外の作業(産品の性質を実質的に変更する加工など)が行われていないことが条件です。
- 証明: 第三国を経由した場合は、通し船荷証券(Through B/L)や、経由国の税関が発行した証明書等を提出し、貨物の同一性が保たれていることを証明する必要があります。
3. 手続き要件:原産地証明書
上記の条件を満たすことの証明として、「原産地証明書(Certificate of Origin : C/O)」の提出が不可欠です。
- 様式: GSPで用いられる国際様式は「フォームA(Form A)」と呼ばれます。
- 提出: 原則として、輸入申告の際に税関に提出します。
- 免除規定: 課税価格の総額が20万円以下の物品については、提出が免除されます(関税暫定措置法施行令第27条)。
まとめ – 特恵関税を正しく理解する
- 法的根拠: GSPのルールは、特別法である「関税暫定措置法」で定められた一方的・暫定的な措置である。
- 二層構造: 「一般特恵」と、より優遇される「LDC特別特恵」がある。
- EPAとの関係: LDC受益国は常に有利な方を選択できるが、一般特恵受益国はEPA税率がGSP税率以下の場合、GSPを選択できない。
- 3つの条件: ①対象国、②対象品目、③原産地・輸送要件を満たすこと。
- 必須書類: 手続きの鍵は「原産地証明書(フォームA)」。直送原則の証明には通し船荷証券(Through B/L)なども用いられる。
次回予告
このシリーズでは、今後も受験生がつまずきやすい論点を一つずつ丁寧に解説していきます。
次回は、関税法等の頻出論点マスターシリーズ第4回として、「保税地域」について、その種類や役割、そこで認められる行為などを体系的に解説していきます。
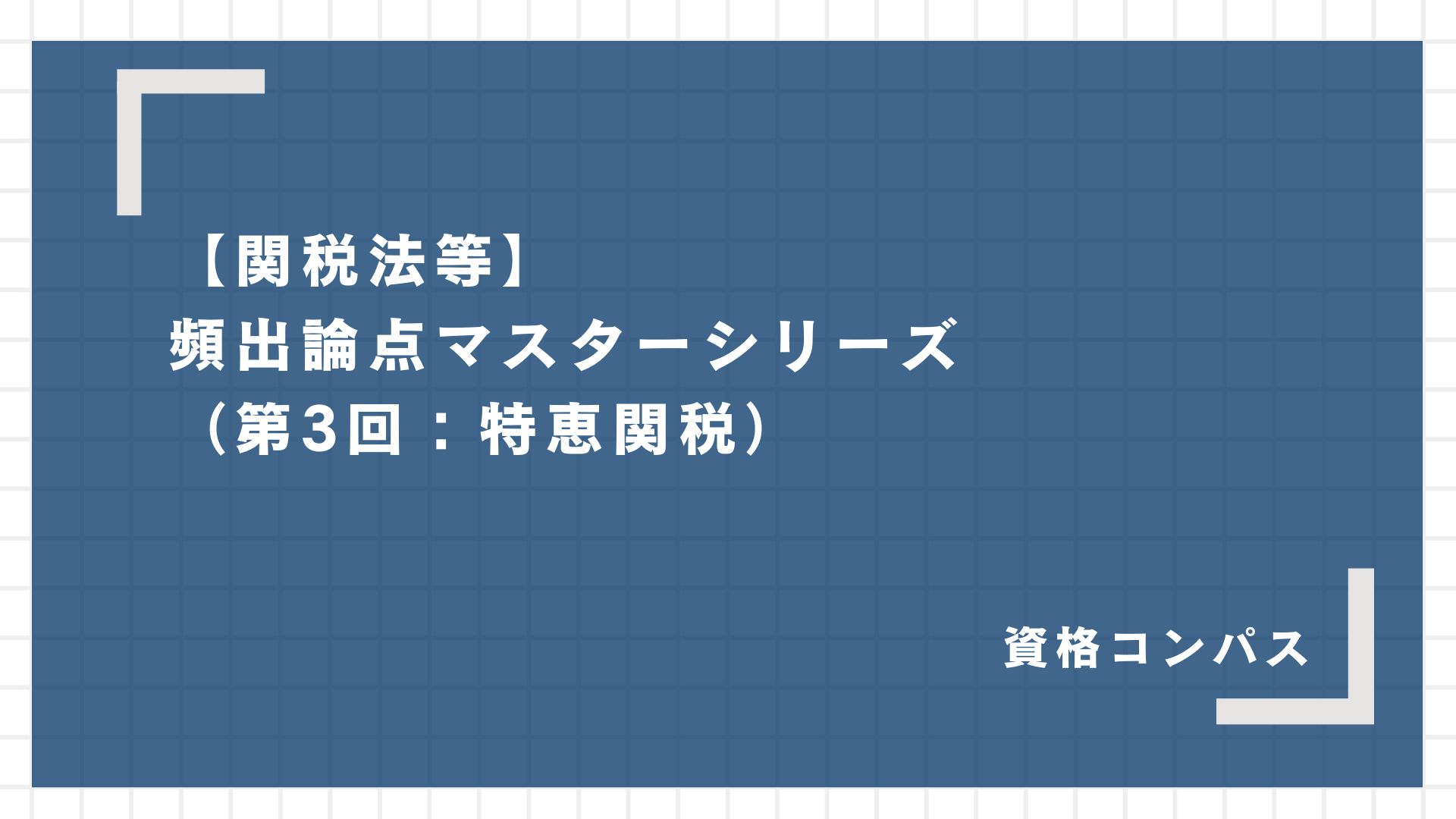




コメント