「通関業法」と聞くと、難しそうな法律のイメージがありませんか?
実は、通関業法は通関士試験の合格の土台を築く、絶対に落とせない戦略科目です。他の科目に比べて学習範囲が限定的なため、満点を目指して徹底的に学習することで、最難関科目である「通関実務」などの学習に時間を充てる余裕が生まれます。
このシリーズでは、そんな通関業法の重要条文を1つずつ、初学者の方にも分かりやすく丁寧に解説していきます。
記念すべき第1回は、法律の全体像を掴むための「第1章 総則」と、通関ビジネスを始めるためのルールを定めた「第2章 許可」に関する部分を学びます。2025年6月1日施行の法改正にも対応した最新の内容でお届けします。
この記事を読み終える頃には、通関業法の骨格となる部分が明確に理解できているはずです。
▼通関業法の全体像と学習のポイントは、こちらの完全攻略ガイドで解説しています。
通関業法とは?試験における位置づけ
まず、通関業法がどのような法律で、試験においてどういった位置づけなのかを確認しましょう。
通関業法とは、一言でいえば「通関業務に関するルールを定めた法律」です。
輸出入を行う際には、必ず税関の許可を得る必要がありますが、その手続きは非常に専門的で複雑です。そこで、輸出入者に代わって手続きを代行する専門家、それが「通関業者」です。
通関業法は、この通関業者がビジネスを行う上でのルールや、通関のプロである「通関士」の役割などを定めています。
合格の土台を築くための最重要科目
通関士試験は3科目すべてで原則6割以上の得点が必要であり、1科目でも基準を割ると不合格となります。
- 通関業法
- 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(関税法等)
- 通関書類の作成要領その他通関手続の実務(通関実務)
この中で「通関業法」は、学習範囲が狭く、努力が点数に直結しやすい科目です。しかし、それは「楽な科目」という意味ではありません。むしろ、合格のためには満点近くのスコアを確保することが不可欠な、合格の土台となる科目と位置づけるべきです。
ここで盤石な基礎を築くことが、合格への最短経路となります。
第1章 総則(第1条~第2条)のポイント
それでは、さっそく条文を見ていきましょう。
まずは、この法律の基本方針を示す「総則」です。
第1条(目的)- この法律のゴールを知る
(目的)
第一条 この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置その他必要な事項を定めることにより、通関業務の適正な運営を図り、もつて関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。
この条文のゴールは、貨物の通関に関する手続の「適正」かつ「迅速」な実施を確保することです。
「適正」は国の安全や税収の確保、「迅速」は貿易の円滑化という、時に相反する二つの要請を、専門家である通関業者が調和させることを制度的に保障しています。
第2条(定義)- 重要キーワードの意味を正確に押さえる
法律の学習では「言葉の定義」が非常に重要です。第2条では、この法律で使われる基本的な用語の意味が定められています。
| 用語 | 定義(分かりやすく要約) | 権限者 |
|---|---|---|
| 通関業務 | 他人の依頼を受けて行う、通関手続の代理・代行、税関の処分に対する不服申立ての代理・代行、税関への主張・陳述の代理・代行など。 | – |
| 通関業者 | 第3条第1項の許可を受けて、通関業務を営む者。 | 財務大臣 |
| 通関士 | 第31条第1項の確認を受けて、通関業者の通関業務に従事する者。 | 税関長 |
ポイントは、全国規模の事業活動を認める「通関業者」の許可は国レベルの財務大臣が、より現場に近い個人の監督である「通関士」の確認は地域ごとの税関長が行う、という役割分担です。この違いは試験で頻繁に問われます。
第2章 許可 – ビジネスを始めるための重要条文
ここからが本番です。
通関業を始めるための「許可」の制度について、その全体像を理解しましょう。
第3条(通関業の許可)- ビジネスを始めるための大原則
(通関業の許可)
第三条 通関業務を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。
通関業を始めるには財務大臣の許可が必要です。
この許可権者は、かつての「税関長」から2016年に変更されました。これは単なる権限移管ではなく、営業区域制限の撤廃という大きな制度改革の結果です。旧制度では税関長の許可はその管轄内でのみ有効でしたが、現行法では一つの許可で全国どの税関に対しても業務が可能となり、通関サービス市場の競争促進と貿易円滑化が図られています。
第5条(許可の基準)- ポジティブリストの理解
許可を得るには、単に「欠格事由に該当しない」だけでは不十分です。第5条に定められた、許可を与えるための積極的な基準(ポジティブリスト)を満たす必要があります。
【許可の積極的基準(要約)】
- その事業の経営の基礎が確実であること。
- その事業の人的構成に照らして、業務を適正に遂行する能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
つまり、財産的な基盤がしっかりしていて、信頼できる人材が揃っていることが求められるのです。
第6条(欠格事由)- ネガティブリストの理解【最重要】
第5条の基準を満たしていても、第6条で定められた欠格事由(ネガティブリスト)に一つでも該当すると許可は受けられません。この条文は試験で最も問われやすい超重要項目です。
| 欠格事由(要約) | 許可を受けられない期間 | 法令上の根拠(第6条) |
|---|---|---|
| 禁錮以上の刑の執行を終えてから | 3年を経過しない者 | 第3号 |
| 関税法・租税法違反による罰金刑の執行を終えてから | 3年を経過しない者 | 第4号 |
| 監督処分により許可を取り消されてから | 2年を経過しない者 | 第8号 |
| 暴力団員でなくなってから | 5年を経過しない者 | 第7号 |
| 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | – | 第2号 |
【重要法改正情報】2025年6月1日から「禁錮」は「拘禁刑」に
2025年6月1日に施行される改正刑法により、現在の「懲役刑」と「禁錮刑」は廃止・統合され、新たに「拘禁刑(こうきんけい)」が創設されます。これに伴い、上表の「禁錮」という文言は「拘禁刑」に読み替える必要があります。2025年度以降の試験を受験される方は必ず押さえておきましょう。
この歴史的な法改正の詳しい背景や、試験で注意すべき「法の不遡及」の原則については、以下の特集記事で徹底解説しています。
第17条(名義貸しの禁止)
(名義貸しの禁止)
第十七条 通関業者は、自己の名義をもつて、他人に通関業務を営ませてはならない。
これは、許可を受けた通関業者が、許可のない他人に自分の名前を貸して商売をさせてはいけない、というルールです。
「許可の消滅」と「許可の取消し」の決定的な違い
許可が効力を失う場面には、法的性質が全く異なる2つのパターンがあります。この違いを理解することは、法の体系を把握する上で非常に重要です。
| 比較項目 | 許可の消滅(第10条) | 許可の取消し(第11条/第34条) |
|---|---|---|
| 法的性質 | 自動的な法的効果の発生 | 懲罰的な行政処分 |
| 発生原因 | 客観的な事実の発生(死亡、法人の解散、事業の廃止など) | 法令違反、不正な許可取得など |
| 法的効果 | 許可の効力が将来に向かって失われる。 | 許可が強制的に剥奪される。 →新たに2年間の欠格事由に該当する |
「取消し」はペナルティであり、その後2年間は再び許可を得られなくなる、という連関性をしっかり理解しておきましょう。
まとめ:総則と許可をマスターするための学習ポイント
今回は、通関業法の土台となる「総則」と「許可」に関する条文を解説しました。法改正が多く、情報が古いと致命傷になる分野です。必ず最新の情報で覚え直してください。
- 許可制度の全体像: 許可を得るには、第5条の積極的基準を満たし、かつ第6条の欠格事由に該当しないことが必要。
- 許可権者(第3条): 財務大臣。法改正の背景(営業区域制限の撤廃)も理解する。
- 欠格事由(第6条): 「3年」「2年」「5年」など期間の数字を正確に暗記。2025年6月からの刑法改正(拘禁刑)も要チェック。
- 許可の終了: 自動的に効力を失う「消滅(第10条)」と、行政処分である「取消し(第11条/第34条)」を明確に区別する。
これらの内容は、通関業法の学習を進める上での基礎となります。
独学で法律の条文を読み解くのは骨が折れる作業ですが、一つ一つ丁寧に意味を理解すれば、必ず得意科目にできます。もし、独学での学習に限界を感じる場合は、学習戦略を見直してみるのも一つの手です。
次回は、同じく第2章の中から、許可を受けた後の「通関業務」や「通関士」に関するルールを解説していきます。
この記事が、あなたの合格への羅針盤となることを願っています。
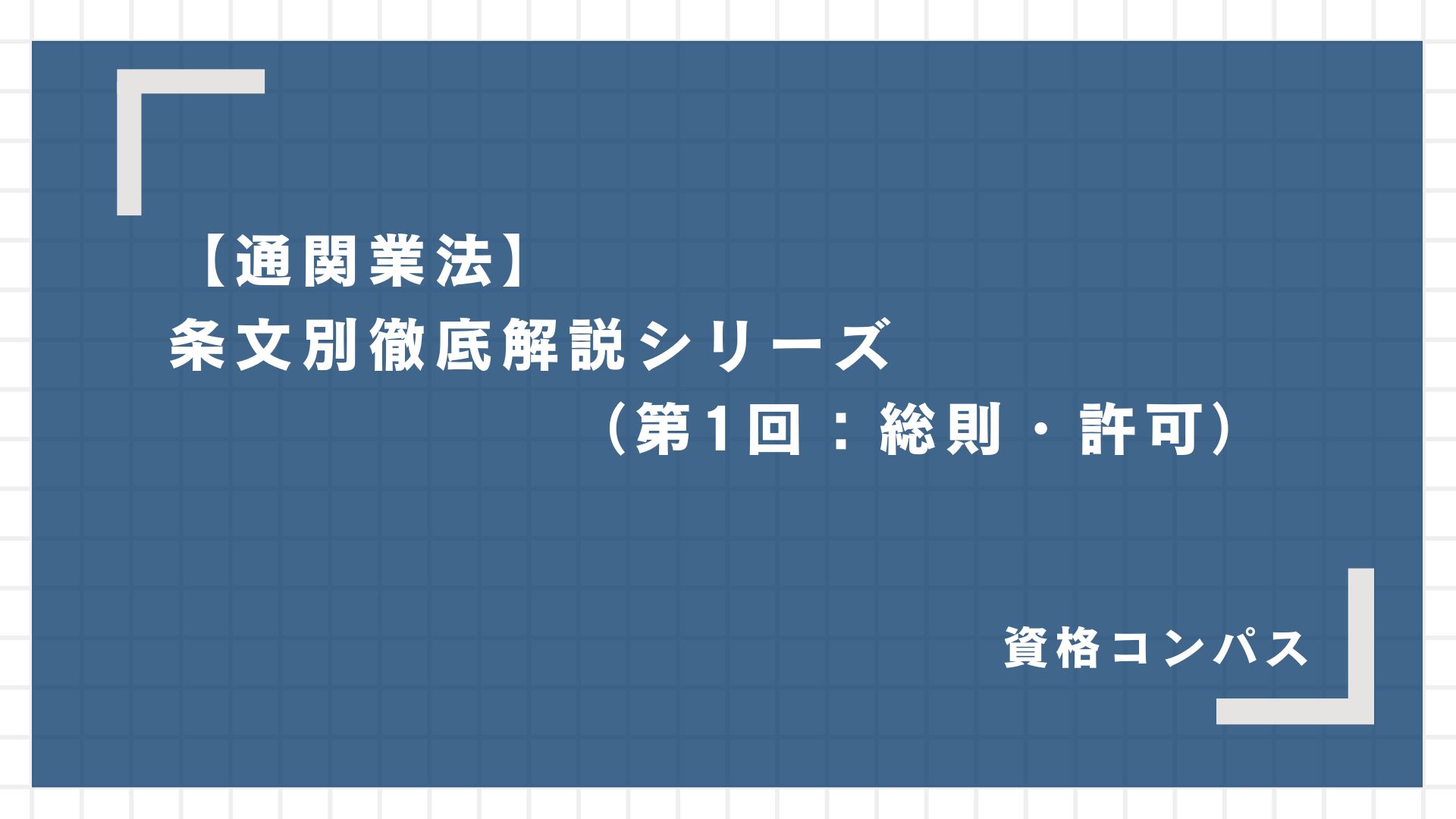

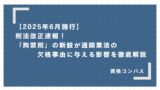




コメント