通関士試験の合格への羅針盤、「資格コンパス」へようこそ。
全5回にわたってお届けしてきた通関業法解説シリーズも、今回でいよいよ最終回です。
最終回は、行政上のペナルティとは一線を画す「罰則(刑事罰)」と、その他に見逃せない「雑則」について解説します。特に罰則規定は、近年の刑法改正を受けて内容が大きく変わっています。最新の正確な知識をここでしっかり押さえましょう。
▼通関業法の全体像と学習のポイントは、こちらの完全攻略ガイドで解説しています。
「罰則」- 刑事罰としてのペナルティ
これまで学んできた「監督処分」や「懲戒処分」は、行政庁(財務大臣)が科す行政罰でした。これから学ぶ「罰則」は、裁判所の手続きを経て科される刑事罰であり、両者は性質が全く異なります。
| 項目 | 行政罰(監督・懲戒処分) | 刑事罰(罰則) |
|---|---|---|
| 誰が科すか | 行政庁(財務大臣) | 裁判所 |
| 処分の内容 | 業務停止、許可の取消し、業務従事の禁止など | 拘禁刑、罰金 |
| 前科 | つかない | つく |
【一歩進んだ理解】行政罰と刑事罰は併科されることも
重要なのは、行政罰と刑事罰は目的と手続きが異なるため、一つの違反行為に対して両方が科される(併科される)可能性があるという点です。例えば、不正な手段で許可を得た場合、財務大臣から「許可の取消し」(行政罰)を受け、さらに裁判所から「拘禁刑または罰金」(刑事罰)を科されることがあります。
【重要】拘禁刑の適用時期について
2022年の刑法改正により、従来の「懲役刑」は廃止され、新たに「拘禁刑」が創設されました。この新しい拘禁刑が適用されるのは、施行日である2025年6月1日以降に行われた犯罪行為に限られます。 それ以前の行為に対しては、引き続き従来の懲役刑が適用されます。この「法の不遡及」の原則は、試験対策上、極めて重要です。
この刑法改正が通関業法の欠格事由や罰則に与える具体的な影響や、受験生が注意すべき学習上のポイントについては、こちらの速報記事で詳しく解説しています。
【現行法】第41条 – 最も重い罰則(無許可営業・秘密漏洩など)
通関業法で最も重い刑事罰が定められているのが第41条です。
【罰則の内容】
一年以下の拘禁刑 または 百万円以下の罰金【対象となる主な行為】
- 無許可で通関業を営んだ者(通関業法第41条第1項第1号)
- 不正の手段により通関業の許可を受けた者(通関業法第41条第1項第2号)
- 監督処分による業務停止命令に違反した者(通関業法第41条第1項第3号)
- 正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らした者(通関業法第19条違反)(通関業法第41条第1項第4号)
【試験のポイント】秘密漏洩は「親告罪」
上記のうち、秘密を漏らした罪は親告罪(しんこくざい)です(通関業法第41条第2項)。これは、被害者(秘密を漏らされた顧客など)からの告訴がなければ起訴できない犯罪を意味します。裁判の公開によって秘密がさらに公になるという二次被害を防ぐため、訴追の判断を被害者の意思に委ねる、被害者保護の趣旨に基づいています。
【現行法】第44条 – その他の罰則(名義貸しなど)
名義貸しなどの違反行為に対しても、刑事罰が定められています。
【罰則の内容】
三十万円以下の罰金【対象となる主な行為】
- 名義貸しを行った通関業者(通関業法第17条違反)または通関士(通関業法第33条違反)
両罰規定(第45条) – 法人と個人を同時に罰するルール
従業員が違反行為を行った場合、その行為者本人だけでなく、雇い主である法人や事業主も罰せられることがあります。これを両罰規定といいます(通関業法第45条)。ただし、事業主が従業員の違反を防止するために必要な監督を尽くしていたことを証明すれば、処罰を免れる可能性があります。
「雑則」- 秘密を守る義務(第19条)
最後に、罰則規定と密接に関わる、専門家としての基本的な義務を確認しましょう。
【条文のポイント】
通関業者(その役員及び従業員を含む。)及び通関士は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者でなくなつた後においても、同様とする。(通関業法第19条)
重要なのは、この義務が退職後も続く終生の義務である点です。違反した場合は、第41条の刑事罰の対象となり、かつ親告罪として扱われます。
通関業法シリーズの総まとめ
全5回にわたり、通関業法の重要条文を解説してきました。各回の要点を振り返り、知識を総整理しましょう。
- 第1回(許可): 通関業を始めるには財務大臣の許可が必要。欠格事由に該当しないことが大前提。
- 第2回(業務・通関士): 営業所には通関士の設置が義務。通関士は重要書類を審査・記名する。
- 第3回(営業・届出): 届出義務の根拠条文(第12条と第22条)の役割分担を正確に理解する。
- 第4回(監督・懲戒): 財務大臣による行政罰。事業者への最重処分は「許可の取消し」、通関士個人へは「二年間の業務従事禁止」。
- 第5回(罰則・雑則): 違反行為には拘禁刑や罰金といった刑事罰も。行政罰との併科もあり得る。
【最重要】関係者別の帳簿書類保存義務の比較分析
シリーズを通して学んだ知識の中で、特に混同しやすく、試験で狙われやすいのが帳簿の保存期間です。以下の表で、誰が、どの法律に基づき、何年間保存する義務を負うのかを完璧に整理しましょう。
| 義務者 | 通関業者 | 輸入者 | 輸出者 |
|---|---|---|---|
| 根拠法規 | 通関業法 及び同法施行令 | 関税法 及び同法施行令 | 関税法 及び同法施行令 |
| 法的目的 | 業務運営の監督 | 関税の適正な課税・徴収 | 貿易管理・コンプライアンス |
| 対象 | 通関業務に関する帳簿・書類 | 輸入貨物に関する帳ぼう・書類 | 輸出貨物に関する帳ぼう・書類 |
| 帳簿保存期間 | 3年間 | 7年間 | 5年間 |
| 書類保存期間 | 3年間 | 5年間 | 5年間 |
| 法的根拠(条文) | 通関業法第22条 施行令第8条 | 関税法第94条 | 関税法第94条 |
なぜ輸入者の帳簿保存期間だけが7年と長いのか?
これには関税の「更正」ができる期間(除斥期間)が関係しています。税関は、原則5年まで遡って納税額を修正できますが、不正行為があった場合は最大7年まで遡って追徴課税ができます。輸入者に7年間の帳簿保存を義務付けるのは、この税関の調査権の実効性を担保するためです。
通関業法の学習、お疲れ様ました!
この記事が、あなたの合格への羅針盤となることを願っています。
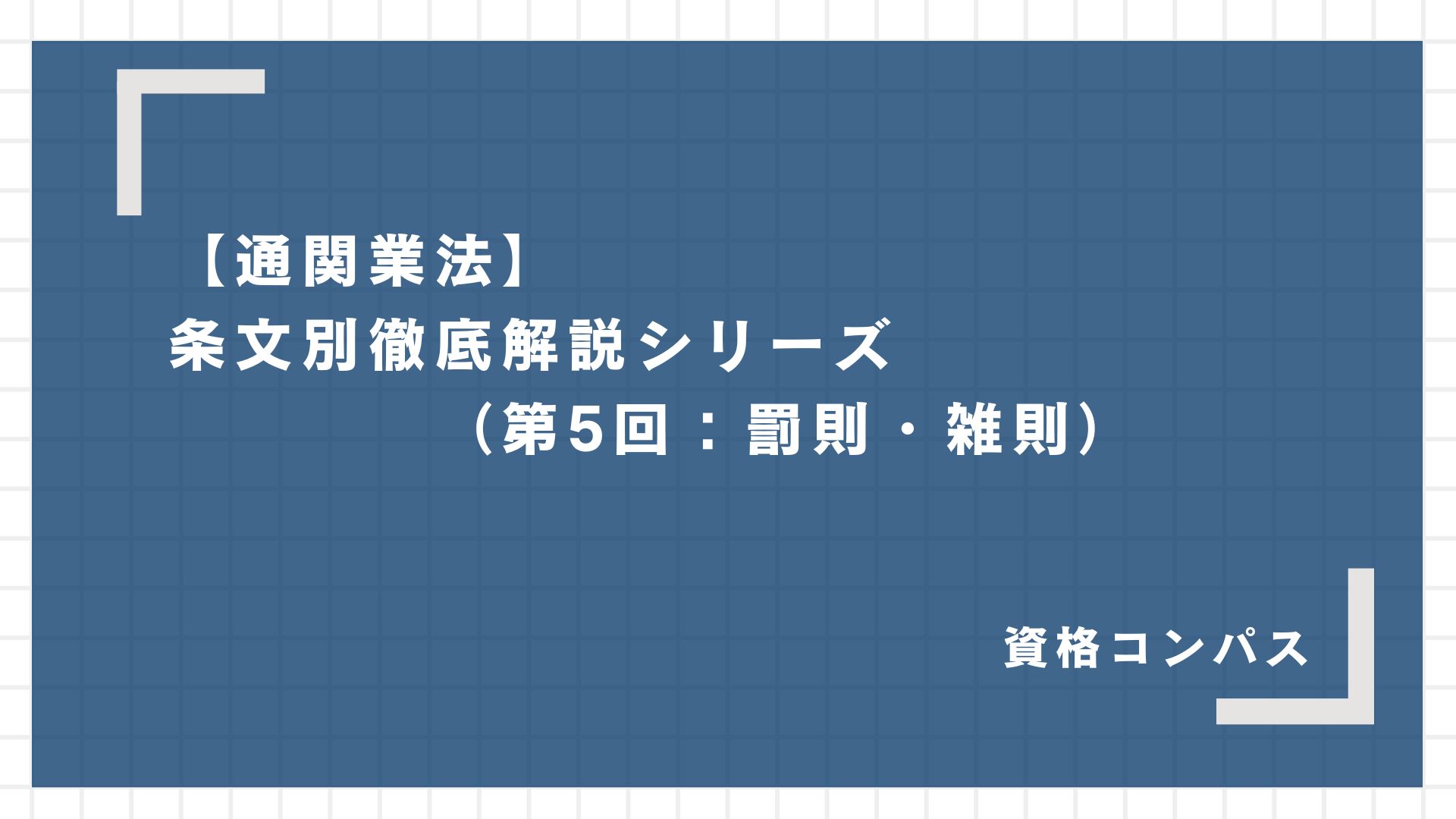


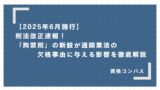





コメント