ようこそ、「資格コンパス」へ。このシリーズでは、通関士試験の難関科目「関税法等」の頻出論点を、一つずつ丁寧に解き明かしています。
前回の第7回では、「修正申告と更正の請求」について、納税者の義務と権利という二元的な視点から、その精緻な手続きを解説しました。
さて、第8回のテーマは「減税・免税・戻し税」です。
これは、特定の政策目的を達成するため、あるいは特定の状況下での公平性を確保するために、本来課されるべき関税を安くしたり(減税)、ゼロにしたり(免税)、一度納付した関税を返還したり(戻し税)する、各種の特例制度です。
種類が多く複雑に見えますが、それぞれの制度が「なぜ」存在するのかという目的を理解すれば、体系的に整理することができます。この記事で、複雑な減免税制度を得点源に変えましょう。
なぜ関税を安くする制度があるのか? – 政策目的のバランス
これらの特例制度は、主に以下のような政策目的を達成するために設けられています。
- 産業振興・国際競争力強化
- 文化・学術・社会政策
- 国際条約・外交儀礼
- 課税の公平性
- 行政の効率化と貿易円滑化
これらの目的は時に、「国内産業の保護」という関税本来の機能と対立します。各制度の具体的な要件や例外規定は、これらの異なる政策目的間のバランスを取るための調整の結果として定められています。
【減税】税額が低くなるケース
変質・損傷減税制度の正しい理解(関税定率法第10条)
- 目的: 課税の公平性
- 内容: 貨物の変質・損傷が発生した時期によって、手続きが異なります。
- 輸入申告「前」: 特別な手続きは不要。損傷後のありのままの状態で申告すればよい。
- 輸入申告「後」、輸入許可「前」: この場合の手続きは、関税法に基づく「更正の請求」です。関税定率法第10条が減税を認める実体的な権利を定め、関税法がその権利を実現する手続きを定めています。
- 輸入許可「後」、保税地域蔵置中: この場合は、納付済み関税の「払い戻し(戻し税)」となります。ただし、「災害その他やむを得ない理由」による場合に限定されます。
海外で加工・修繕した貨物の減税(関税定率法第11条)
- 目的: 産業振興
- 内容: 日本から輸出した貨物が、海外で加工・修繕され、原則1年以内に日本に再輸入される場合に、輸出時の価値に相当する部分の関税が軽減される制度です。
- 【重要】: 海外で「加工」された貨物にこの制度を適用するには、「本邦においてその加工をすることが困難であると認められるもの」という重大な要件があります。これは、国内産業の空洞化を防ぐ目的があり、単に海外の方がコストが安いといった経済的理由は含まれません。
【免税】税金がゼロになるケース
① 特定用途免税(関税定率法第15条)
特定の公益性の高い用途に使うことを条件に関税が免除されます。
- 例: 学術研究用品、博物館に陳列する標本、宗教用品、慈善・救じゅつ用寄贈物品、日本赤十字社へ寄贈された医療機器など。
- 【重要】: 免税の適用を受けた貨物は、輸入許可の日から2年間、税関の監督下に置かれます。この期間内に、承認された用途以外に使用・譲渡した場合は、免除された関税が直ちに徴収されます。
② 再輸出免税(関税定率法第17条)
一定期間内に再び輸出されることを前提に関税が免除されます。原則として、輸入許可の日から1年以内に再輸出する必要があります。
- 例: 修理される貨物、展示会への出品物、職業用具、国際的な運動競技会や国際会議で使用される物品など。
- 【重要】: この免税は「条件付き」であるため、税関長は、免除される関税額に相当する担保の提供を求めることができます。
③ 無条件免税(関税定率法第14条)
【最重要論点】個人輸入における課税価格の特例(0.6掛けルール)
少額貨物免税を理解する上で絶対に欠かせないのが、個人が自身の個人的な使用のために輸入する物品(個人輸入品)の課税価格の計算特例です。
この場合、課税価格は「海外における小売価格 × 0.6」として計算されます。
したがって、少額貨物免税の基準となる「課税価格1万円以下」という条件は、個人輸入の場合、海外小売価格が16,666円以下であれば満たされることになります(16,666円 × 0.6 ≒ 1万円)。
この「0.6掛けルール」を知っているか否かは、試験問題の正誤を直接左右します。
【注意】少額貨物免税が適用されない品目
課税価格の合計額が1万円以下の貨物は、原則として関税が免除されます。しかし、この免税には、国内産業保護の観点から適用除外品目が定められています。これらはたとえ個人輸入で課税価格が1万円以下であっても免税とはならず、関税が課されます。
- 主な適用除外品目:
- 革製品(ハンドバッグ、旅行用具、手袋など)
- ニット製衣類(セーター、カーディガン、Tシャツなど)
- 履物(革靴、運動靴など)
- 米などの穀物とその調製品
- ミルク、クリームなどとその調製品
- ハムや牛肉缶詰などの食肉調製品
- たばこ、精製塩
【コラム】越境ECの拡大と少額貨物免税制度の見直し
近年、越境電子商取引(EC)の利用が世界的に急拡大し、日本でも少額輸入貨物の件数が急増しています。この状況は、もともと個人間の贈答品などを想定していた少額貨物免税制度が、現代の商取引の実態と合わなくなってきているという課題を生んでいます。
特に問題視されているのが、国内外の事業者間の競争条件の公平性です。国内の事業者が商品を販売すれば消費税が課されるのに対し、海外のEC事業者から個人が1万円以下の商品を輸入する場合は免税となるため、国内事業者が不利な立場に置かれるとの指摘があります。
こうした課題に対応するため、財務省は2025年6月に「急増する少額輸入貨物への対応に関するワーキンググループ」を設置し、適正な課税のあり方についての議論を開始しました。EUやオーストラリアなどでは既に同様の免税措置の見直しが進んでおり、日本でも今後の制度改正の動向が注目されます。
この制度見直しの具体的な論点と、未来の通関士の仕事に与える本質的な影響については、以下の未来予測記事で詳しく考察しています。
【戻し税】一旦納付した関税が返ってくるケース
① 違約品等の戻し税(関税定率法第20条)
- 目的: 課税の公平性
- 内容: 輸入した貨物が、品質などが契約内容と相違していた(違約品)ため、再輸出するか、税関長の承認を受けて廃棄した場合に、納付済みの関税が還付される制度です。
- 手続き: 原則として、輸入許可の日から6ヶ月以内(やむを得ない理由があれば最長1年まで延長可)に、貨物を保税地域に入れて手続きを行う必要があります。
② 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税(関税定率法第19条の3)
- 目的: 貿易円滑化(中継貿易の促進)
- 内容: 関税を納付して輸入した貨物が、国内で消費されることなく、輸入された時と同一の性質・形状のまま、原則として輸入許可の日から1年以内に再輸出される場合に、納付済み関税が還付される制度です。
【絶対混同注意】関税の「戻し税」と消費税の「輸出還付」
これら「戻し税」は、あくまで「関税」という国境税の払い戻し制度であり、税関の管轄です。
これとは全く別に、輸出取引に伴い、仕入れ時に支払った「消費税」の還付を受ける「輸出免税(ゼロ税率)」制度がありますが、こちらは国内消費税の国際的な二重課税を排除するための税額調整であり、税務署の管轄です。両者は、その税哲学(消費地課税主義)からして全く異なる制度です。
まとめ – 減免税制度の体系的整理【最終決定版】
| 分類 | 主な制度名 | 法的根拠(関税定率法) | 政策目的 | 主要な要件(期間等) | 試験対策上の重要注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減税 | 変質・損傷減税/戻し税 | 第10条 | 課税の公平性 | 申告後・許可前は関税法に基づく「更正の請求」。許可後は「戻し税」。 | 申告前の損傷は本制度の対象外。許可後の戻し税は「災害等」が要件。 |
| 減税 | 加工・修繕再輸入減税 | 第11条 | 産業振興 | 日本から輸出→海外で加工・修繕→原則1年以内に再輸入。 | 「加工」の場合、国内での実施が困難な場合に限られるという要件を見落とさないこと。 |
| 免税 | 特定用途免税 | 第15条 | 文化・社会政策 | 指定された特定の用途に供すること。 | 【重要】輸入許可後2年間の用途監視期間がある。 |
| 免税 | 再輸出免税 | 第17条 | 貿易円滑化 | 原則1年以内に再輸出すること。 | 【重要】関税額相当の担保提供を求められる場合がある。 |
| 免税 | 無条件免税(少額貨物) | 第14条 | 行政の効率化 | 課税価格の合計額が1万円以下。 | 【最重要】個人輸入の場合、課税価格 = 海外小売価格 x 0.6。適用除外品目(革製品, ニット, 履物, 特定食料品等)の暗記は必須。 |
| 戻し税 | 違約品等の戻し税 | 第20条 | 課税の公平性 | 原則6ヶ月以内に保税地域に搬入し、再輸出または廃棄。 | やむを得ない理由があれば最長1年まで延長可能。 |
| 戻し税 | 同一状態再輸出戻し税 | 第19条の3 | 貿易円滑化 | 輸入時と同一状態で、原則1年以内に輸出。 | 消費税の輸出還付(管轄:税務署)とは全く別の制度であることを本質から理解すること。 |
次回予告
このシリーズでは、今後も受験生がつまずきやすい論点を一つずつ丁寧に解説していきます。
次回は、関税法等の頻出論点マスターシリーズ第9回として、「不服申立て」について、税関の処分に不服がある場合に、納税者が取りうる法的な救済手段を詳しく解説していきます。
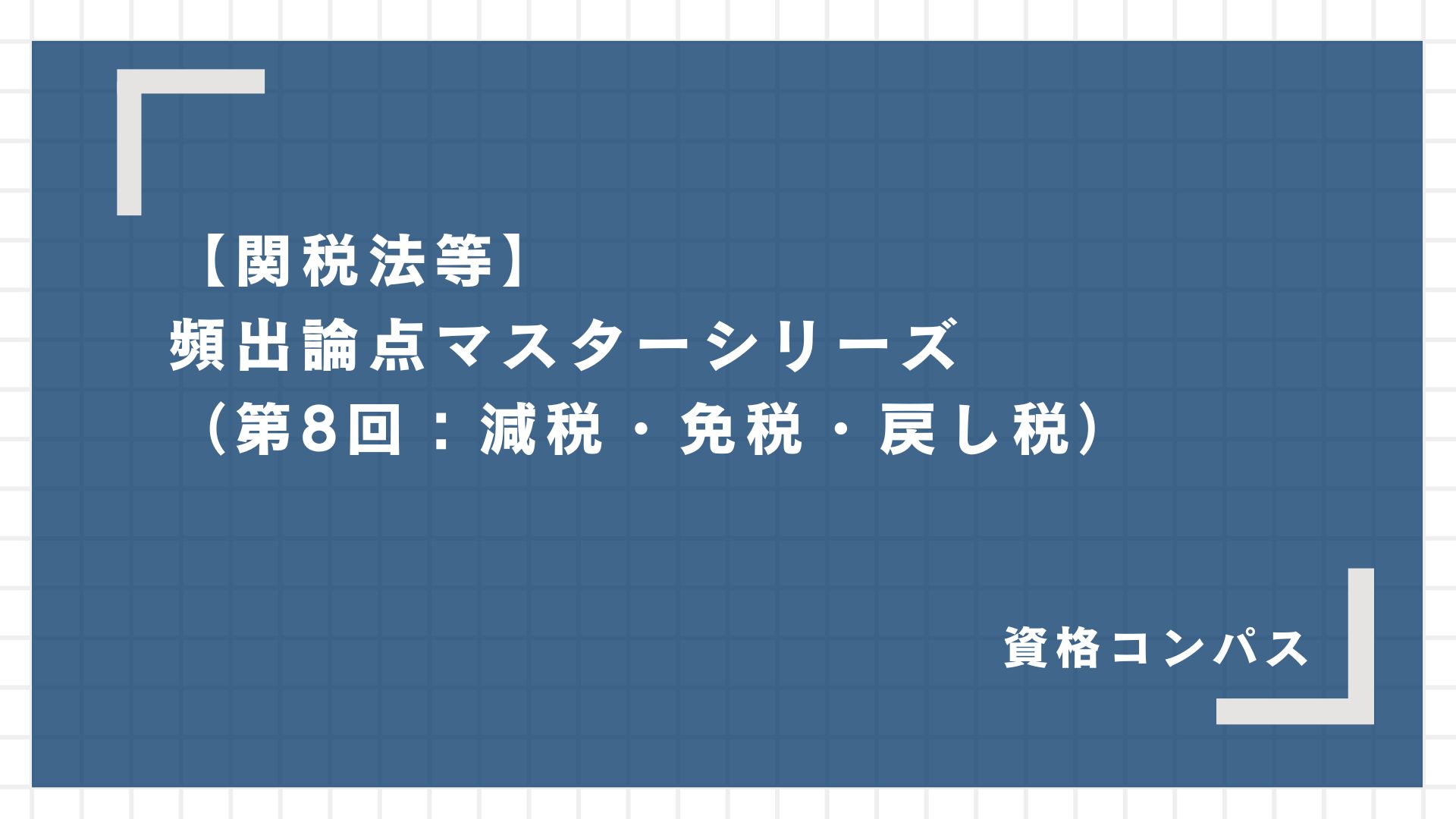

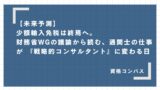



コメント