通関士試験の合格への羅針盤、「資格コンパス」へようこそ。
このシリーズ「計算問題パターン別攻略法」では、合否を分ける通関実務の計算問題をテーマ別に徹底解説しています。
前回の第1回では、すべての計算の土台となる「課税価格の計算」について、その法的根拠と4つのステップを学びました。
▼ 第1回の記事はこちら
さて、第2回のテーマは、前回算出した課税価格を用いて、最終的な納税額を導き出す「関税額の計算」です。
一見すると単純な掛け算に見えますが、ここには受験生を惑わす「端数処理」という重要なルールが存在します。この記事を読めば、ミスが多発する端数処理のルールを完璧にマスターし、複数品目の計算にも自信を持って対応できるようになります。
▼【通関実務】の全体像と学習法はこちらの完全攻略ガイドで解説しています。
関税額計算の基本公式 – 3つの要素を理解する
まず、関税額を算出するための基本的な構造を理解しましょう。計算は、以下の3つの要素から成り立っています。
- 課税価格: 前回学んだ、関税を計算するための基礎となる価格です。
- 関税率: 貨物の種類(HSコード)によって法律で定められた税率です。試験では通常、問題文で与えられます。
- 為替レート: 外貨建ての価格を円に換算するためのレートです。
これらを用いて、以下の基本公式で関税額を計算します。
関税額 = 課税価格 × 関税率
しかし、実際の試験では、この単純な式に「端数処理」というルールが加わることで、計算の正確性が問われます。
【試験の核心】端数処理のルールを制する
関税額の計算で最もミスが発生しやすいのが「端数処理」です。このルールは、「①課税価格の確定」と「②関税額の確定」という2つの段階で、それぞれ異なる法律に基づいて適用されます。
STEP 1: 課税価格の端数処理(1,000円未満切り捨て)
まず、関税率を掛ける前の「課税価格」そのものに端数処理を行います。
- ルール: 課税価格の合計額が1万円以上の場合、その1,000円未満の端数を切り捨てます。課税価格の合計額が1万円未満の場合は、切り捨てを行いません。
- 法的根拠: 関税法 第118条第1項
- 具体例:
- 課税価格が
1,234,567円の場合 →1,234,000円 - 課税価格が
9,876円の場合 →9,876円(切り捨てなし)
- 課税価格が
STEP 2: 関税額の端数処理(100円未満切り捨て)
次に、STEP 1で処理した後の課税価格に関税率を掛けて算出した「関税額」に端数処理を行います。
- ルール: 算出した関税額に、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
- 法的根拠: 国税通則法 第119条第1項
- 具体例:
- 算出した関税額が
12,345円の場合 →12,300円 - 算出した関税額が
987円の場合 →900円
- 算出した関税額が
この「課税価格は1,000円未満、関税額は100円未満」という2段階の切り捨てルールは、絶対に暗記してください。
【実践演習】複数品目を一度に申告する場合の「3ステップ計算」
実際の試験では、複数の品目を一つの申告書で輸入するケースが頻繁に出題されます。この場合の計算手順は、受験生が特に混乱しやすいポイントです。
結論から言うと、正しい手順は「①品目ごとに課税価格を処理し、②品目ごとに関税額を算出し、③最後に全品目の関税額を合計して端数処理する」です。
【例題】
ある輸入者が、以下の2品目を一つの輸入申告書で申告する。納付すべき関税額の合計はいくらか。
- 品目A: 課税価格
555,555円、関税率5% - 品目B: 課税価格
444,444円、関税率10%
【正しい解法:3ステップ計算】
- STEP 1: 品目ごとに課税価格の端数処理を行う
- 品目A:
555,555円→555,000円(1,000円未満切り捨て) - 品目B:
444,444円→444,000円(1,000円未満切り捨て)
- 品目A:
- STEP 2: 品目ごとに関税額を算出する(この段階では端数処理しない)
- 品目Aの関税額:
555,000円 × 5% = 27,750円 - 品目Bの関税額:
444,000円 × 10% = 44,400円
- 品目Aの関税額:
- STEP 3: すべての関税額を合計し、最後に100円未満を切り捨てる
- 関税額の合計:
27,750円 + 44,400円 = 72,150円 - 最終的な納付税額:
72,150円→72,100円(100円未満切り捨て)
- 関税額の合計:
【よくある間違い】
× 各品目の関税額を先に端数処理してしまう
品目A: 27,750円 → 27,700円
品目B: 44,400円 → 44,400円
合計: 27,700円 + 44,400円 = 72,100円
(この例では偶然答えが一致しましたが、端数によっては結果が変わるため、プロセス自体が間違いです)
従量税と混合税 – 例外的な計算方法
これまで解説してきたのは、価格を基準とする「従価税」の計算方法です。しかし、関税には例外的に他の方式も存在します。
- 従量税: 価格ではなく、貨物の数量、重量、容積などを基準に課税する方式です。(例:1kgあたり〇円)
- 混合税: 従価税と従量税を組み合わせ、いずれか高い方の税額、または両方の合計額を課税する方式です。
これらの税が適用される品目(例:一部の農産物など)は、国内産業保護のため、輸入品の価格が不当に安い場合でも最低限の税金を確保する目的で設定されています。試験では、問題文の指示に従って計算すれば対応できます。
まとめ:端数処理を制する者が計算問題を制する
今回は、関税額の計算方法、特に合否を分ける「端数処理」のルールに焦点を当てて解説しました。
- 2段階の端数処理: 課税価格は1,000円未満、最終的な関税額は100円未満を切り捨てる。
- 複数品目の計算: ①課税価格処理 → ②関税額算出 → ③合計して最終処理、という3ステップを徹底する。
- 法的根拠: 課税価格の処理は関税法、関税額の処理は国税通則法と、根拠となる法律が異なることも知識として押さえておきましょう。
関税額が正しく計算できて、初めて次のステップに進めます。次回は、輸入品に課されるもう一つの重要な税金である「輸入消費税の計算」について詳しく解説していきます。
▼ 関連知識を深める
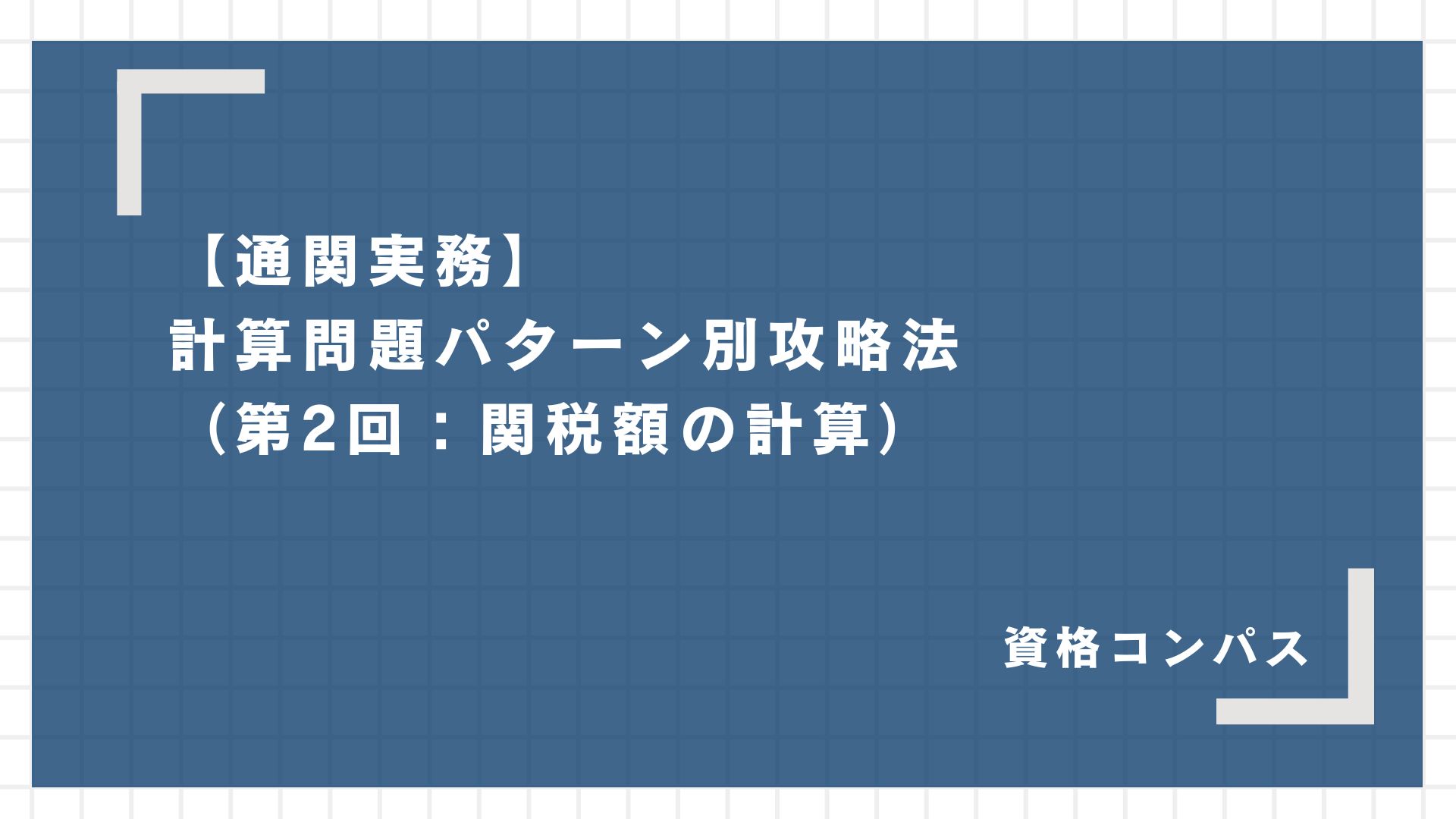

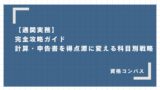

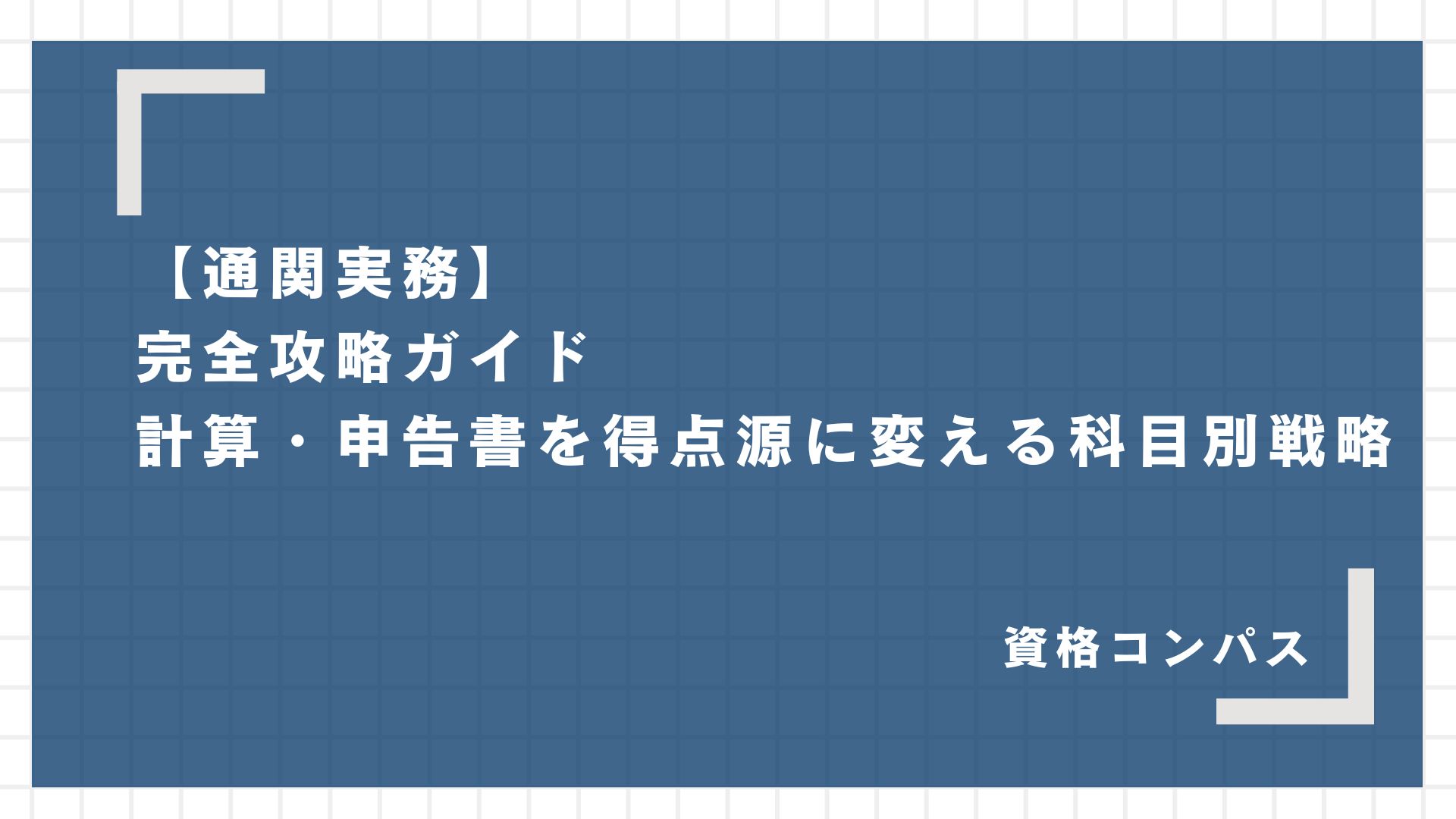



コメント