ようこそ、「資格コンパス」へ。このシリーズでは、通関士試験の難関科目「関税法等」の頻出論点を、一つずつ丁寧に解き明かしています。
前回の第4回では、「保税地域」について、5つの種類とその複雑なルールを、法政策的な背景と共に解説しました。
▼ 第4回の記事はこちら
さて、第5回のテーマは「輸入してはならない貨物」です。
これは、通関士が「貿易のゲートキーパー」として果たすべき、最も重要な役割の一つに関わる知識です。単なる税金の計算だけでなく、国の安全や経済秩序を守るという、通関士の責任の重さを象徴する規定でもあります。
安易な語呂合わせに頼ると重大な知識の欠落を生むこの論点について、法的根拠である関税法第69条の11に基づき、完全かつ正確に解説します。
なぜ「輸入してはならない貨物」の規定があるのか? – 保護法益の序列
そもそも、なぜ特定の貨物の輸入を法律で厳しく禁止する必要があるのでしょうか。その目的は、国が守るべき利益(保護法益)にありますが、それらには法律上の重要度に応じた序列が存在します。
- 最上位の利益(国家の安全・公安): 銃砲や麻薬など、国家の存立や国民の生命に直接的な脅威を与えるもの。
- 下位の利益(経済秩序など): 偽ブランド品など、主に経済的な利益を害するもの。
この序列は、後述する罰則の重さに明確に反映されています。この構造を理解することが、単なる丸暗記から脱却する第一歩です。
【試験の核心】関税法第69条の11 全リスト完全解説
試験対策上、輸入が禁止されている品目を、条文の号レベルで正確に覚えることは必須です。この法律は、新たな社会的脅威に対応するため改正が重ねられてきた「生きている法」であり、その構造自体が重要です。
| 保護法益 | 法的根拠 | 具体的な貨物 |
|---|---|---|
| 公衆衛生・公安 | 第1号 | 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具 |
| 第1号の2 | 指定薬物(医療等の用途に供するものを除く) | |
| 国家の安全・公安 | 第2号 | けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾、けん銃部品 |
| 第3号 | 爆発物 | |
| 第4号 | 火薬類 | |
| 第5号 | 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に規定する特定物質 | |
| 公衆衛生 | 第5号の2 | 一種病原体等及び二種病原体等 |
| 経済秩序・信用 | 第6号 | 偽造・変造・模造の貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手、有価証券、偽造カード |
| 公序良俗 | 第7号 | 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(わいせつ物) |
| 第8号 | 児童ポルノ | |
| 経済秩序 (知的財産権) | 第9号 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権、育成者権を侵害する物品 |
| 第9号の2 | 外国の事業者が国内の者(事業者を除く)に郵送等する商標権又は意匠権を侵害する物品 | |
| 第10号 | 不正競争防止法に違反する物品(他人の商品の形態を模倣した物品など) |
【最重要改正】知的財産権侵害物品と「認定手続」
2022年10月の法改正で、知的財産権侵害物品の規制が大きく変わりました。この改正の核心を正確に理解しましょう。
2022年改正の精緻な法的メカニズム
改正前は、個人が「個人的な使用目的」で模倣品を輸入する場合、輸入者本人の行為が商標法上の「業として」の侵害行為に該当せず、税関での差止めが困難でした。
この抜け穴を塞ぐため、改正法は「海外の事業者が、郵送等により日本国内に(模倣品を)持ち込む行為」自体を、権利侵害行為と定義しました。これにより、税関は国内の受取人が個人か事業者かを問わず、貨物を没収できるようになりました。
ただし、この規制強化には極めて重要な限定があります。それは、この新しいルールが適用されるのは、商標権と意匠権を侵害する物品に限られるという点です。
個人受取人への罰則は?
この新しい規制によって模倣品が没収される場合でも、事業者ではない個人の受取人自身が刑事罰の対象となるわけではありません。
差止めの前提となる「認定手続」
税関による差止めは、恣意的に行われるものではなく、「認定手続」という厳格な行政手続を経て行われます。これは、税関が侵害の疑いがある貨物を発見した場合に、輸入者と権利者の双方に意見を述べる機会を与え、提出された証拠を精査した上で、侵害物品に該当するか否かを最終的に「認定」する、準司法的なプロセスです。
発見された場合の法的措置と罰則の階層
禁止品が発見された場合、行政処分と刑事罰という二つの次元で厳しい措置が取られます。
行政措置:没収・廃棄と「積戻し」の厳格な制限
- 没収・廃棄: 関税法違反に係る禁止品は、原則として必要的没収(必ず没収される)の対象です。税関長はこれを没収し、輸入者の費用負担で廃棄を命じることができます。
- 積戻し: 輸入者が主体的に行う「積戻し申告」は、常に可能な選択肢ではありません。特に、国際条約との整合性を図るため、商標権または著作権を侵害すると認定された貨物については、原則として積戻しが許可されません。「見つかったら送り返せばよい」という安易な考えは通用しません。
【重要】罰則の二階層構造とその論理
関税法第109条は、違反の対象となる貨物の種類によって、罰則に明確な階層を設けています。
| 階層 | 対象貨物(関税法第69条の11第1項の号) | 最高刑罰(関税法第109条) |
|---|---|---|
| 第1階層 | 第1号~第6号(麻薬、銃砲、偽造通貨等) | 10年以下の懲役 もしくは 3,000万円以下の罰金 |
| 第2階層 | 第7号~第10号(児童ポルノ、知的財産権侵害物品等) | 10年以下の懲役 もしくは 1,000万円以下の罰金 |
なぜ罰金の上限額に3倍の開きがあるのでしょうか?
これは、懲役刑が密輸という行為そのものの悪質性(主観)を罰するのに対し、罰金刑はその行為がもたらす客観的な社会的損害の大きさを反映しているためです。銃砲の流入が社会に与える損害は、偽ブランド品の経済的損害とは質的に異なると、法が判断しているのです。
まとめ – 保護法益の序列から体系的に理解する
- 制度の目的: 「公安」「公衆衛生」「経済秩序」「公序良俗」といった保護法益には序列があり、それが罰則の重さに反映されている。
- 法的根拠: 関税法第69条の11に定められたリストを、号レベルで正確に覚えることが必須。
- 知的財産権: 2022年の個人輸入規制強化は商標権・意匠権に限定される、という適用範囲を必ず押さえる。差止めは「認定手続」を経て行われる。
- 措置と罰則: 発見された場合は必要的没収が原則。商標権・著作権侵害品は積戻しが原則不可。刑事罰は貨物の危険性に応じた二階層構造になっている。
次回予告
このシリーズでは、今後も受験生がつまずきやすい論点を一つずつ丁寧に解説していきます。
次回は、関税法等の頻出論点マスターシリーズ第6回として、「関税の確定・納付・徴収」について、税額がどのように決まり、納付され、そして不足があった場合にどうなるのか、という一連の流れを解説していきます。
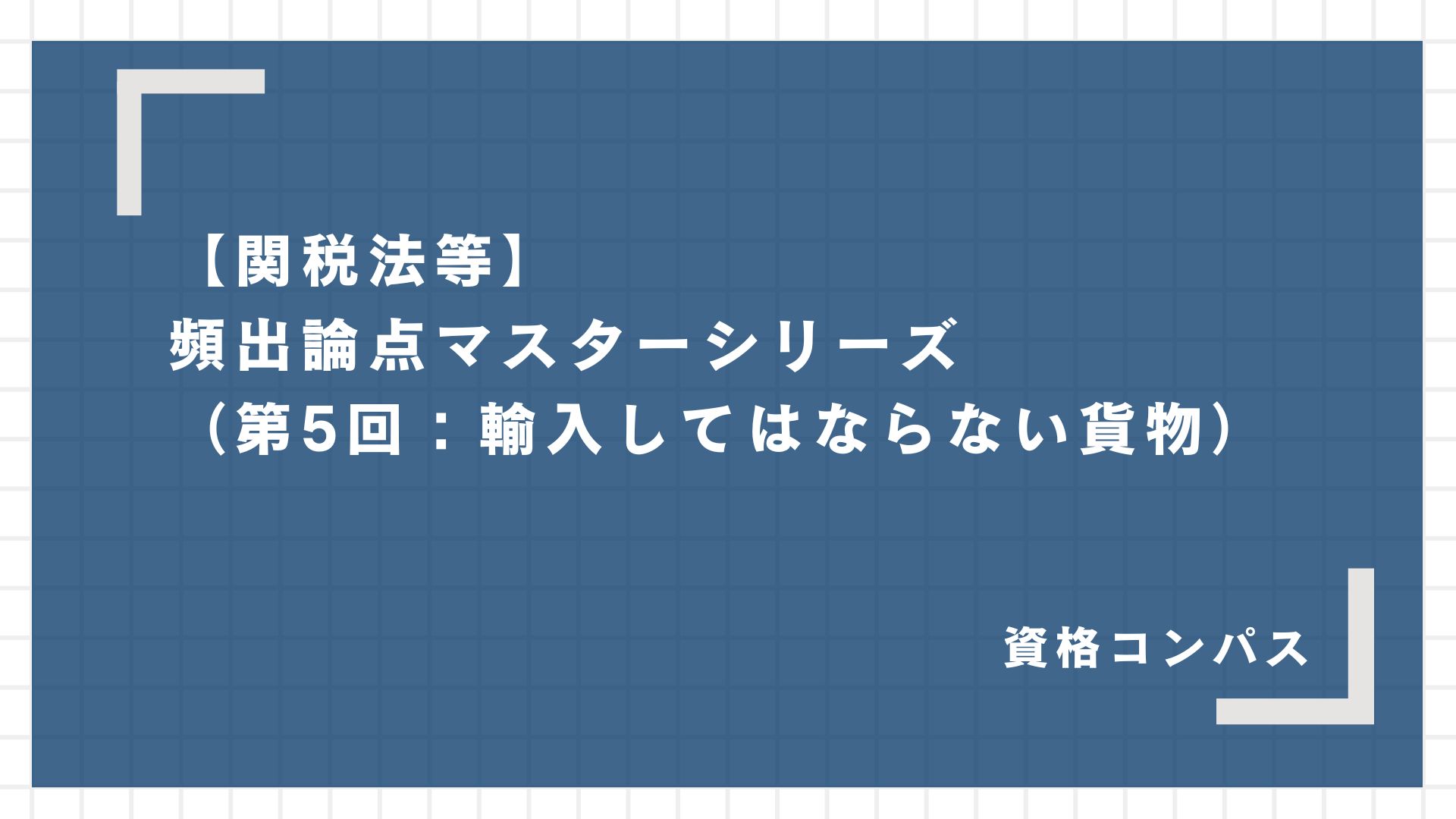




コメント